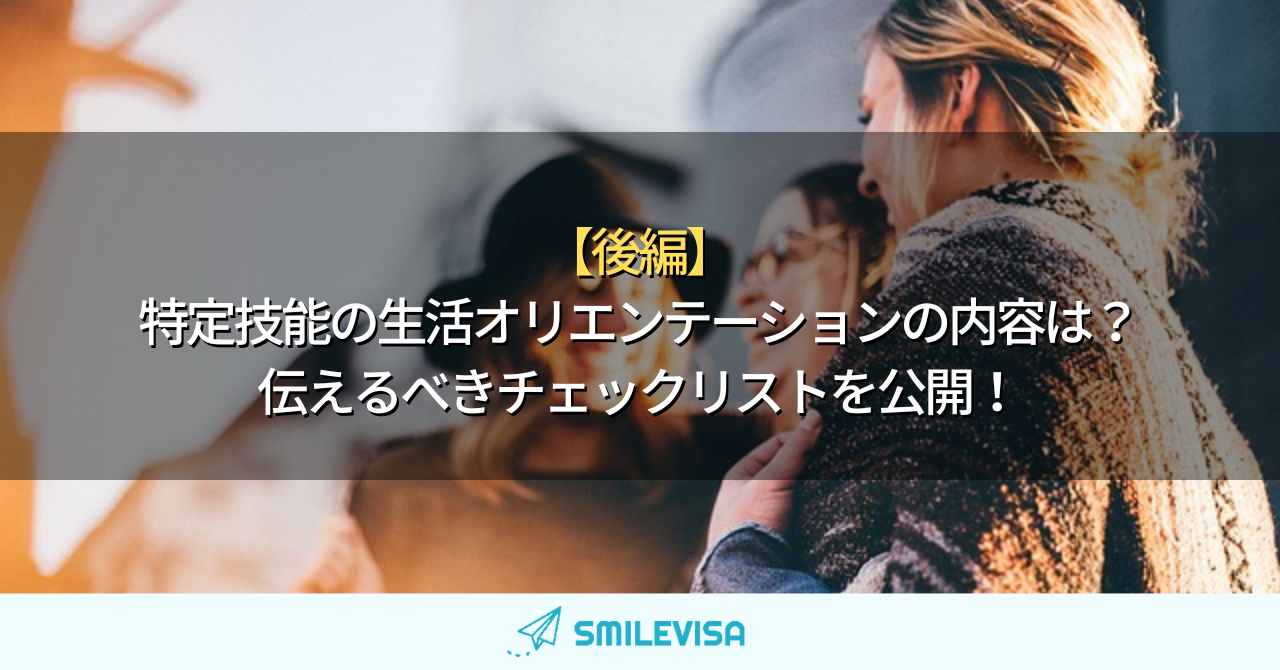目次
こんにちは!SMILEVISAです。
前回、生活オリエンテーションの内容について解説しましたが、今回は後編の記事となります。前編はこちら。
おさらいとして、具体的に生活オリエンテーションで伝えるべき内容は以下の通りでした。
①生活一般に関する事項
②受け入れ企業等、住宅地、社会保障及び税に関する届出
③相談や苦情に対応する者や国、地方公共団体の機関の連絡先
④十分に理解できる言語により医療を受けられる医療機関
⑤防災及び防犯に関する事項や急病等の緊急時における対応
⑥規定違反時の対応方法や法的保護に必要な事項
前編では「①生活一般に関する事項」について説明しましたが、今回の後編記事では②〜⑥について解説していきます。
②受け入れ企業等、住宅地、社会保障及び税に関する届出

外国人は様々な届出をする必要があります。そのため受け入れ企業は、外国人が行う届出について生活オリエンテーションで説明する必要があります。
1.受け入れ企業等に関する届出
以下が起こった場合は、外国人本人が入国管理局に届出をする必要があります。届出の期限は事象が生じてから14日以内です。
外国人本人による届出が必要になるケース
・受入企業から退職した
・受入企業を転職した場合
・受入企業が名称を変更した場合
・受入企業が所在地を変更した場合
・受入企業が消滅した場合
届出の方法はインターネット、窓口に持参、郵送などの方法があります。参考様式はこちらです。
2.住居地に関する届出
以下の場合は在留カードを持参し、それぞれ該当する場所で住居地の届出手続を行います。参考様式はこちら(下記すべての場合で参考様式は共通します)。
・日本へ入国した後
住居地がある市区町村の窓口で住居地届出書を提出します。期限は住居地の決定から14日以内です。
・在留資格変更等
住居地がある市区町村の窓口で住居地届出書を提出します。期限は資格変更から14日以内です。
・住居変更時
変更後の市区町村の窓口で住居地届出書を提出します。期限は移転した日から14日以内です。
参考様式はこちら(上記すべての場合で参考様式は共通します)。
3.社会保障及び税に関する手続き
社会保障に関する手続き
ケース別で手続きが異なります。手続きを行わなかった場合、在留資格申請に通らなくなることがあるため注意が必要です。
・受け入れ企業が適用事業所(※)の場合
健康保険及び厚生年金保険に関する保険料は給与から天引きされます。
※適用事務局というのは、健康保険の適用を受ける事業所のことです。
・受け入れ企業が適用事業所以外の場合、または当該外国人が離職する場合
この場合、国民健康保険及び国民年金に関する手続は外国人本人が行います。具体的に届出が必要な時期と書類は以下の通りです。
手続きが必要となるタイミング
- 在留資格認定証明書交付申請時
- 在留資格変更許可申請時
- 在留期間更新許可申請時
地方出入国在留管理局に提出する書類
a. 被保険者記録照会回答票
b .下記いずれか
国民年金保険料領収証書の写し(過去2年分)
※こちらを提出する場合、a. 被保険者記録照会回答票の提出は不要になります。
もしくは
被保険者記録照会(納付Ⅱ)
税に関する手続き
外国人に日本の税に関する手続きについて説明します。未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があるため注意が必要です。
・源泉徴収、特別徴収制度について説明する
所得税、住民税は原則として給与から天引きされることを外国人に説明します。
・住民税納付の仕組みについて説明する
離職後の翌年まで納税義務があることを外国人に説明します。(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税開始します)住民税は前年の所得に応じて計算されるため、離職後翌年まで納税義務があります。
※離職後の納税は離職後の納税は一括納税や納税管理人制度の利用も可能です。一括納税制度についてはこちらのページで説明されています。
一括納税を利用することで、退職時に勤務先(財務等)に申し出ることで、天引きされる予定だった住民税を一括で支払うことが可能になります。
納税管理人とは納税者の代わりに確定申告を提出、税務署からの連絡を受ける人のことです。納税管理人を選んだ場合には、税務署等へ届出書を提出します。
※転職により離職する場合は、転職先で未納税額を給与から天引きできます。
その他
その他、日本の社会保障制度について外国人に説明します。具体的には以下の内容です。
・個人番号(マイナンバー)制度の仕組みや手続き
マイナンバーは日本国内での社会保障、税、災害対策の分野で利用されるものです。マイナンバーカードはコンビニでの住民票の写し等の証明書の取得など、各種サービスに利用できます。マイナンバーの申請方法はこちらです。
・自転車防犯登録の方法
店頭又はインターネットでの購入、他人等から譲り受けた場合は、自転車販売のあるホームセンター、または自転車専門店に持っていくことで登録ができます。外国人の持つ自転車が盗難または撤去された場合は、印鑑と防犯登録番号控えを持ち交番へ行きます。
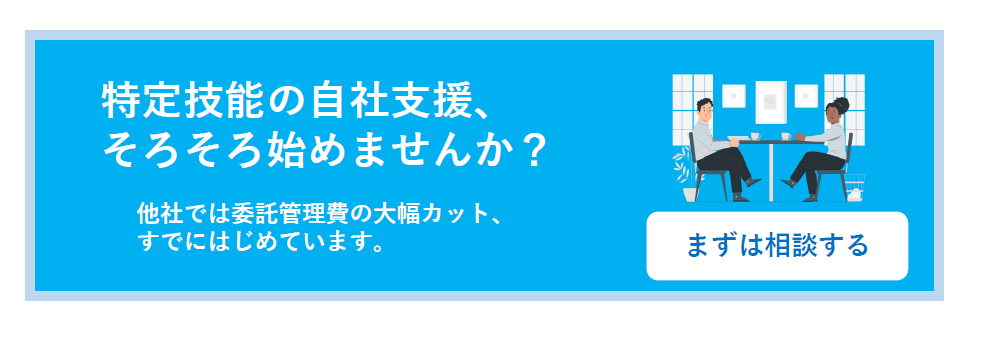
③相談や苦情に対応する者や国、地方公共団体の機関の連絡先

外国人が日本での生活について相談できる機関や人を紹介します。具体的には以下の通りです。
1.支援担当者の連絡先
支援担当者の氏名、電話番号、メールアドレスを外国人に伝えます。LINEやFacebook等も活用するとなお良いです。他にも「困ったときに頼れる人の情報は一覧にしておくと便利」と外国人に伝えます。
2.国または地方公共団体の機関の連絡先
具体的には以下の内容を紹介します。
a.地方出入国在留管理局
・入国に関する相談
・在留に関する相談
b.労働基準監督署
・給料の未払いがあるとき
・労働時間・休みの相談
・仕事中にけがをしたとき
c.ハローワーク
・雇用保険の相談
・失業給付の相談
・仕事がないときの相談
d.法務局・地方法務局
・差別やいじめなど、人権に関する問題の相談
e.市役所・区役所など
・住民税の相談
・マイナンバーの発行
f.大使館・領事館
・パスポートを失ったとき
・パスポートが壊れたとき
g.警察署
・犯罪被害の相談
・交通事故事件の相談
h.弁護士会
・日本司法センター
・裁判に関する相談
・法律に関する相談
i.110番通報について
110は事件や事故のときにかける電話番号であることを伝えます。争いや犯罪の時には事件、交通事故などの時には事故です。また電話した際には、いつ、どこで、何があったのか、自分の名前と電話番号を伝えます。
j.119番号通報について
急な病気や怪我のとき(=救急)、火事の時にかける電話番号です。火事なら消防車が、救急なら救急車(病人や怪我人を病院に運ぶ車)が来ます。

④十分に理解できる言語により医療を受けられる医療機関

外国人に伝えるべき事項は以下の通りです。
・病院の名称、所在地及び連絡先
通訳人が配置されていたり、インターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されている病院を伝えるとなお良いです。
・民間の医療保険への加入案内(任意)
外国人向けに、民間の医療保険を提供しているサービスもあります。高額な医療費の支払いに対応したり、安心して医療サービスを受けられるようになるために、本人の希望があれば医療保険を外国人に勧めることもあります。
⑤防災及び防犯に関する事項や急病等の緊急時における対応

外国人に伝えるべき事項は以下の通りです。
・トラブル対応
自然災害や事故への備え、火災の予防について伝えます。
・通報、連絡の方法
110番、119番通報についてや、大使館、警察署、緊急医療機関の連絡先について伝えます。
・緊急時の状況把握
避難場所の説明や、気象情報、避難指示、避難勧告の把握方法について説明します。緊急速報メールの登録も勧めます。
⑥規定違反時の対応方法や法的保護に必要な事項

以下の情報を外国人に伝えます。
・入管法令の知識
在留手続き、みなし再入国制度、在留資格の取り消し、在留カードに関する手続き等について説明します。
・労働関係法令の知識
労働契約、 休業補償制度 、労働保険制度、 労働安全衛生(安全衛生教育等の実施含む)
・未払い賃金の知識
未払賃金に関する立替払制度(※倒産で賃金未払いの状態の労働者に対し、未払賃金の一部を立替払する制度)について説明します。
規則違反の例とその相談先
a.入管法令に関する違反がある場合
在留資格の活動範囲外で収入を得た資格外活動や、正規の在留資格を持たずに収入を得る不法就労者雇用に関しての相談先は、出入国在留管理庁です。
b.労働・雇用に関する法令違反がある場合
賃金の不払いや時間外、休日労働に関する相談先は出入国在留管理庁、労働基準監督署です。
c.人権侵害があった場合
いじめ、差別、パワハラ、セクハラに関する相談先は出入国在留管理庁、法務局・地方法務局です。
d. 年金受給権、脱退一時金制度について
外国人保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上になると老齢年金を受給できます。
脱退一時金とは、日本国籍でない者が、国民年金、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に、日本の住所を失った日から2年以内に請求できるお金のことです。詳しくはこちらの記事で解説しています。
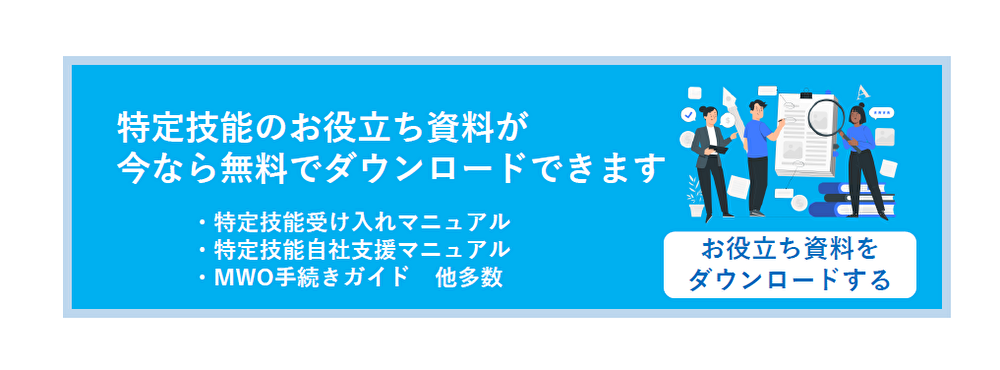
まとめ
今回は以下の生活オリエンテーションで伝えるべき内容のうち、②〜⑥の内容を解説しました。
①生活一般に関する事項について詳しく知りたい方は「特定技能の生活オリエンテーションの内容は?伝えるべきチェックリストを無料で公開!【前編】」の記事をご覧ください。
生活オリエンテーションは受入れ企業(もしくは登録支援機関)が必ず実施するべき項目となっており、外国人にとっても重要な情報提供の場となります。伝えるべきことをしっかり伝えておくようにしましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
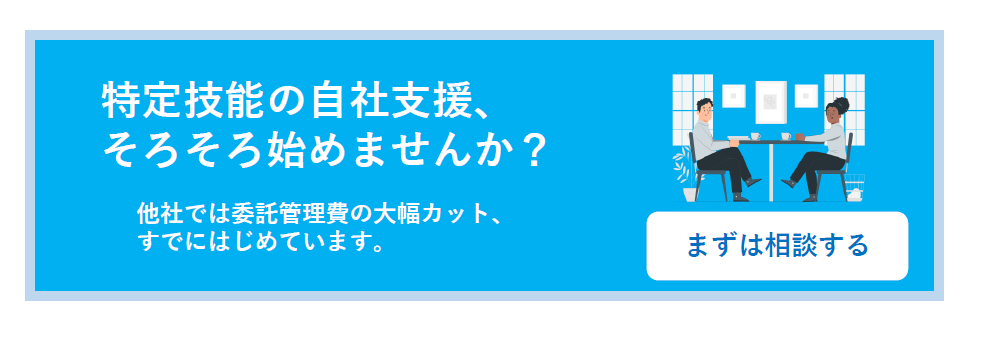
※本記事は現時点(2023年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。