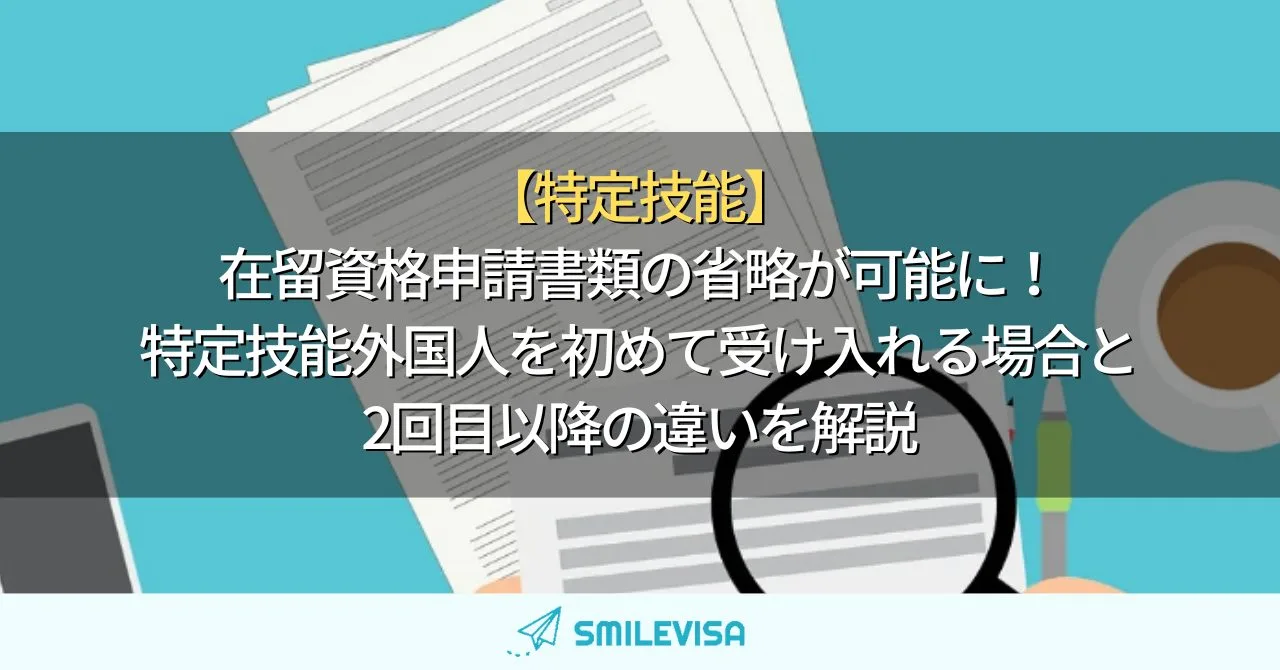目次
みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
特定技能外国人の受入れの際に必要となる申請書類ですが、数が多く準備するのも大変ですよね。しかし、ある一定の条件を満たしていれば特定技能外国人の在留諸申請をする際に書類を省略できるのをご存じでしょうか。
今回の記事では、どのような条件の受入れ企業が申請書類の一部を省略できるのか、実際に省略できる書類は何なのか、その申請方法について詳しくご紹介します!
本記事の最後にて、特定技能の自社管理(内製化)の初めてガイドも無料でダウンロードが可能です。社内で使用して頂ける詳細版となっていますので、ぜひご活用ください。
どのような条件の受入れ企業が申請書類の一部を省略できる?

申請書類の一部を省略できるのは以下の3点のいずれかを満たしている受入れ企業となります。
- 特定技能外国人を初めて受け入れる場合で、一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関
- 同一年度内に特定技能外国人の受け入れ実績がある機関
- 同一年度で、特定技能外国人の受け入れ実績はないが、一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関
以下で詳しく解説していきます。
①特定技能外国人を初めて受け入れる場合(認定申請・変更申請)
特定技能外国人を初めて受け入れる場合は、「一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関」とそうでない場合で必要書類が異なります。
(1)一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関
出入国在留管理庁では、在留諸申請の書類の省略ができる企業の定義について「在留書申請をオンライン申請・各届出を電子届出で行い、一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、書類の省略を認めることとするもの」と述べています。この制度は令和4年8月30日に発表・施行されました。
つまり、ある程度の規模がある企業で、適正な受け入れができると入管から判断された場合は大幅な書類の省略が可能になります。(※一定規模の企業であることの証明が必要です。)
具体的には、下記の通りです。
書類の省略対象となる機関
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4)一定の条件を満たす企業
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6)特定技能所属機関として3年間の継続した受け入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
※過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関に限る
※オンライン申請と電子届出を行うことが必須条件
出入国在留管理庁「在留資格 特定技能」より引用
また、上記の一定の条件を満たす企業等とは?という疑問が出てくるかと思いますが、ここでいう一定の条件とは下記の通りとなります。
一定の条件を満たす企業等について
出入国在留管理庁では、次のいずれかの条件に該当する企業等を対象としています。
- 厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- 経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
- 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
- 国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
出入国在留管理庁「(4)一定の条件を満たす企業(PDF)」より引用
(2)(1)に該当しない場合
上記(1)に該当しない場合は、通常の必要書類を提出します。
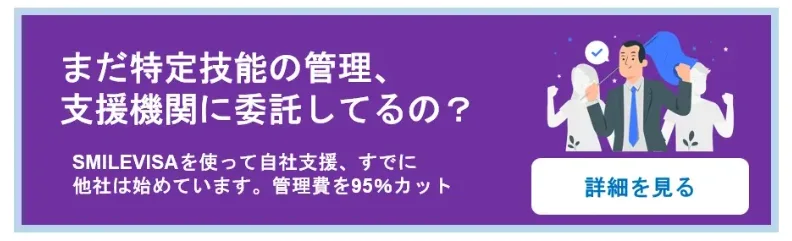
②同一年度内に特定技能外国人の受け入れ実績がある機関(更新申請、2人目以降の認定申請・変更申請)
出入国在留管理庁によると、同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関は、2人目以降の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請において書類を省略できることを発表しています。
つまり、同一年度内に特定技能外国人の受け入れ実績がある場合、受け入れ企業が用意する書類は一切不要です。
この条件に該当する特定技能外国人を受け入れる企業については、提出が必要となるのは外国人本人に関する書類のみです。
ただし、審査時に受け入れ企業の適格性が確認される場合があり、その際には追加で書類の提出をお願いすることがあります。
※「同一年度内に受け入れ実績がある」とは、「特定技能外国人を同一年度の4月1日から3月31日までに1人でも在籍していた期間がある」という意味です。
③同一年度で、特定技能外国人の受け入れ実績はないが、一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関
同一年度で、特定技能外国人の受け入れ実績はないが、一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関の場合は、上記①「特定技能外国人を初めて受け入れる場合」の(1)「一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関」と同様です。
つまり、大幅な必要書類の省略が可能になります。
申請時に省略できる書類は?

申請時に省略できる書類は、「一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関」と「同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関」で異なります。
以下で詳しく解説していきます。
①一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関の場合
上記のいずれかの条件に当てはまる場合、「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において下記の書類の提出が省略できます。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票
(4)特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(5)労働保険料の納付に係る資料
(6)社会保険料の納付に係る資料
(7)国税の納付に係る資料
(8)法人住民税の納付に係る資料
(9)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
②同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関の場合
同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関は、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請において下記の書類の提出が省略できます。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票の写し
(4)特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(5)(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
(6)(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
(7)(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
(8)(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
(9)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
省略するための申請方法は?(一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関)

書類の省略が可能な企業に該当することが分かった場合は、さっそくその旨を申請しましょう。申請の方法は、申請の書類を提出する際に下記の書類を一緒に提出します。
- 書類の省略対象となる機関であることを証明する資料
- 書類の省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)
※こちらは受け入れが初めての場合(初回の申請のみ)提出が必要となります。
上記、それぞれの書類について詳しく説明します。
①書類の省略対象となる機関であることを証明する資料
こちらについては、それぞれどの条件に当てはまるかによって提出書類が変わってきます。たとえば、下記の条件に当てはまる場合に必要な書類についてまとめています。
| 証券取引所に上場している企業 | 四季報の写し(又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) |
| 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)を提出 |
| 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業 (イノベーション創出企業) | 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書 |
その他の条件等について、どのような書類が必要なのか迷う場合は、出入国在留管理庁まで問い合わせて確認することをおすすめしています。こちらのページ「特定技能でわからないことはここで解決!便利サイトや法務省・出入国管理局のお役立ちページまとめ」では、提出書類がわからない場合の問い合わせ先についてまとめています。
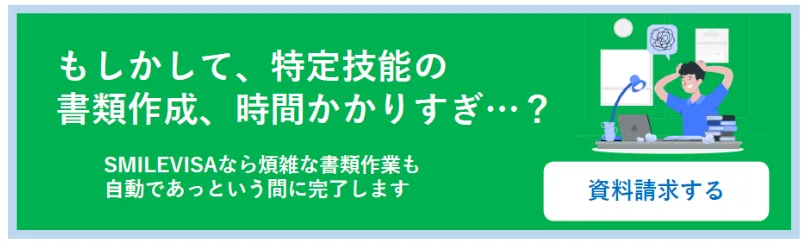
②書類の省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)
こちらについては入管の在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)よりダウンロードが可能です。こちらは形式に沿って内容を確認し、記入をすればOKです。
特定技能の自社支援初めてガイドの無料ダウンロードはこちら
特定技能の自社支援や管理を始める際に、どのようにしたらいいのか、ステップや、準備すべきもの、注意点などについてわかりやすくまとめた資料を無料ダウンロード可能です。こちらの資料は、社内で共有や研修などでお使いいただく際に便利です。
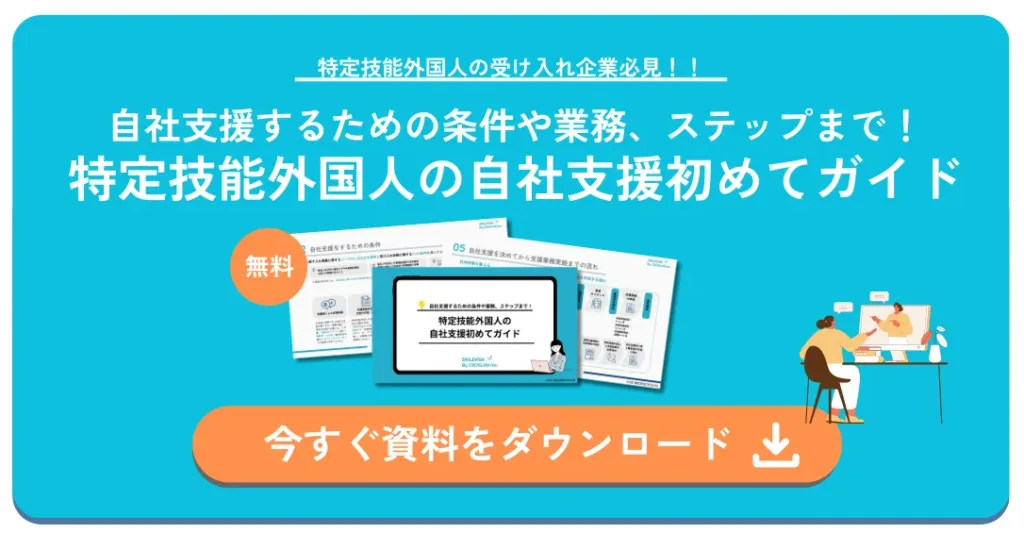
特定技能の書類を省略して、申請を楽にしましょう
以上、一定の条件を満たす企業が省略できる書類やその条件について解説しました。特定技能外国人の書類に関しては量が多く、書類を省略できるものについては確認しておくとスムーズに申請が可能です。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
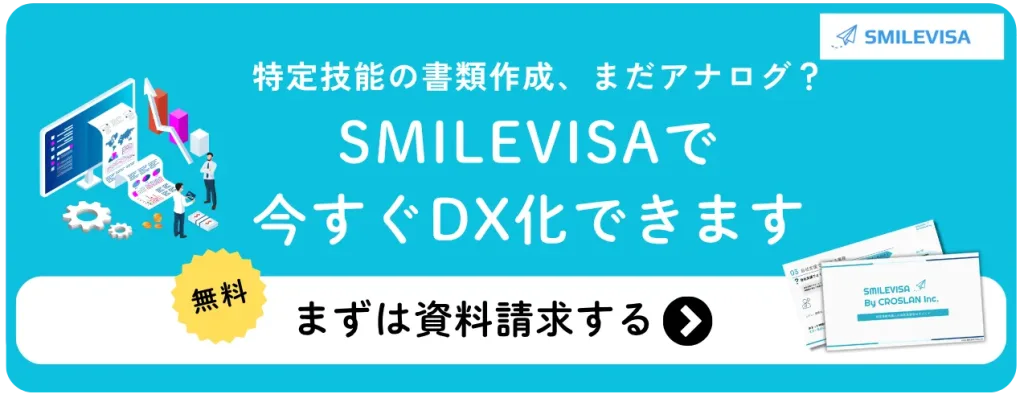
※本記事は現時点(2025年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。