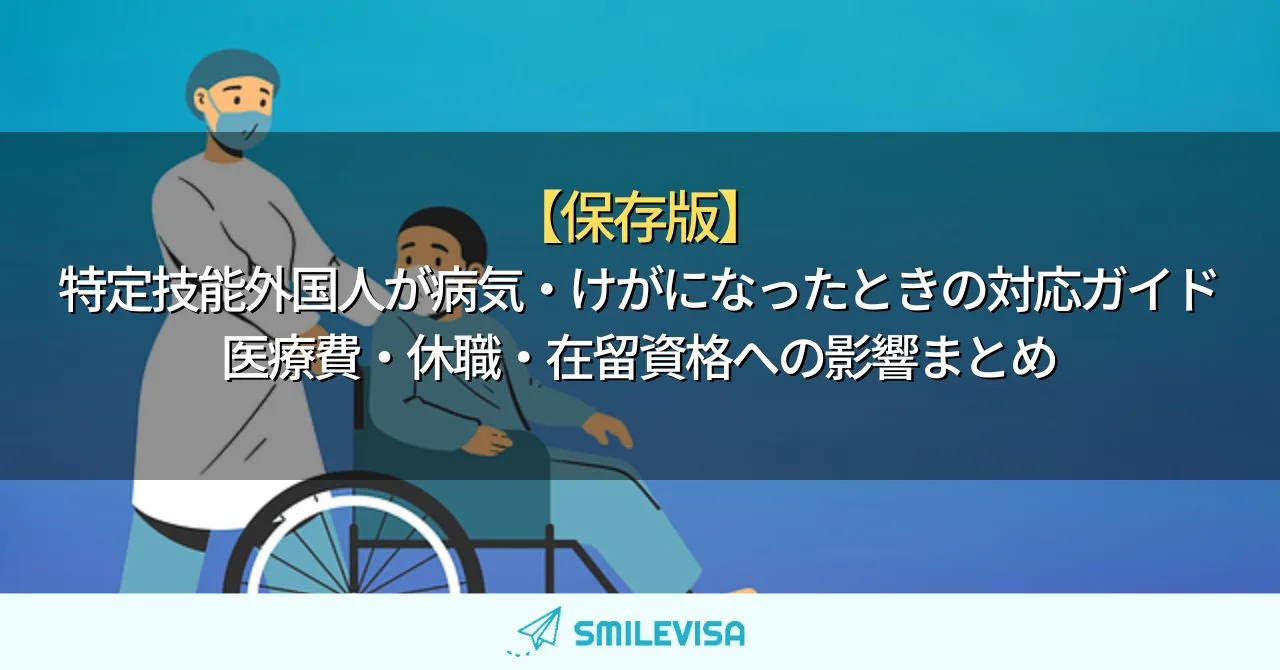目次
特定技能で日本に働きに来ている外国人が、もし病気やけがをしてしまったら――。
こうした不安や疑問は、外国人本人だけでなく、雇用している受け入れ企業にとっても重要な課題です。
本記事では、特定技能で働く外国人が病気やけがをした場合に直面する可能性のある問題と、受け入れ企業の担当者がとるべきその対処法についてわかりやすく解説します。医療費の自己負担、保険の扱い、休職時の制度、在留資格への影響、必要な相談先まで、実務で役立つ知識を網羅しました。
特定技能が病気・けがになった場合に最初にすべきことは?
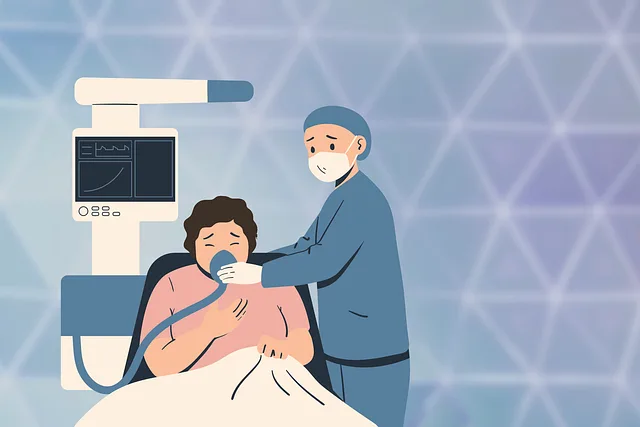
突然の病気やけがに見舞われたとき、受け入れ企業として、適切な判断をする必要があります。医療機関診、緊急連絡先への連絡、公的保険証の確認などを順を追って行うことが重要です。下記、対応についてまとめました。
特定技能外国人が感染症等の病気になった場合
最も多いケースが、感染症(例:インフルエンザ、新型コロナウイルス(COVID-19)結核、ノロウイルス、胃腸炎など)にかかってしまうケースです。
報告があったらまずは就労制限
上記の感染症にかかった場合は、企業は労働安全衛生法や業界ガイドラインに基づき、出勤停止措置を取る必要があります。特に飲食、介護、農業などの対人・集団作業系職種では、感染拡大防止が求められるため、無理に出社させることは絶対にやめましょう。
休職中の対応・給与
感染症により就労が制限された場合、有給を利用するか、もしくは無給になるケースもありますが、就業規則や労使協定により定められた対応がある場合は確認します。また、傷病手当金の申請対象になることがあります(連続4日以上休業が条件)。
ただし、非常にまれですが長期入院や働けない状態が長期にわたって続く場合には、就労継続の意思や今後について入管に説明できるよう、記録を取っておくことをおすすめします。
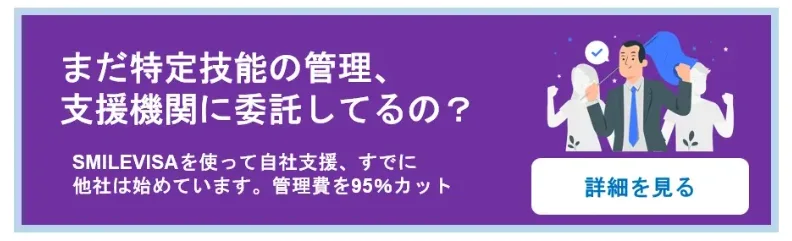
特定技能外国人が怪我をしてしまった場合
特定技能外国人がけがをしてしまうケースも少なくありません。けがの内容や発生場所によって対応が異なりますが、まずは迅速な治療と状況の正確な報告が重要です。
業務中のけが(作業中・通勤中)
業務上のけがの場合は労災保険の対象となり、治療費は原則として全額労災から支払われます。企業は速やかに労災申請を行い、労働者が適切な補償を受けられるように対応しましょう。
私生活中のけが
私生活でのけがは健康保険の適用となります。社会保険や国民健康保険に加入しているかどうかを確認し、病院へ行くように案内しましょう。外国人が一人で病院に行けない場合はサポートすることが望ましいです。
休職中の対応・給与
けがによって就労が制限された場合、労災が適用されれば申請対象になります。しかしながら、私生活の怪我の場合は有給を使用するか、そうでない場合は無給になるため休業期間が4日以上続く場合は傷病手当金(健康保険)申請を検討しましょう。
長期療養や入院の場合の対応
長期間の入院や療養が必要となり就労が困難な場合、在留資格に影響を及ぼすことがあります。企業や支援機関は、医師の診断書や雇用主の意見書など必要な書類を整え、出入国在留管理局に相談しながら適切な対応を進める必要があります。必要な届出等については次の項目で解説します。
病気・けがによる休職・長期療養になってしまったら?

特定技能で働く外国人が病気やけがで休職・長期療養する場合、労働契約の継続や生活費の確保が課題になります。ここでは、長期療養になってしまった場合に必要な手続きについて解説します。
1か月以上の活動停止は入管への報告が必要
特定技能外国人が病気やけがにより、就労(=特定技能としての活動)が1か月以上行えない場合は、在留資格上の義務として、活動未実施の報告が必要になります。報告を怠ると、在留資格更新や変更時に通らなくなる可能性があるため忘れないように行いましょう。
特定技能外国人が1か月以上活動できない場合の報告対応(2025年4月以降対応)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出が必要な書類 | 1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式 第5-14号) |
| 提出先 | 最寄りの出入国在留管理局 |
| 提出のタイミング | 活動停止から1か月経過時点で速やかに提出 |
病気・けがによって特定技能が退職・帰国せざるを得ない場合の対応は?
けがや病気により特定技能外国人が1か月以上就労できず、その後退職となる場合には、通常の退職手続きに加え、出入国在留管理局へ書類を提出する必要があります。以下の表は、退職時に必要となる提出書類とその概要を整理したものです。
けがや病気で1か月以上休んでから退職する場合の提出書類一覧
| 提出書類の名称 | 様式番号 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書 | 第5-14号 | 活動できなかった理由・期間・体調の経過などを報告 |
| 受入れ困難に係る届出書 | 第3-4号 | 雇用主側が就労継続困難と判断したことを正式に報告 |
| 受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書 | 第5-11号 | 退職に至った経緯(けが・病気による療養状況や雇用継続困難な事情)を詳述 |
| 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書 | 第3-1-2号 | 契約終了の事実を報告(退職日・理由などを記載) |
帰国する場合も、けがや病気の場合は移動や手続きが難しくなるケースもあります。その場合は、支援担当者が出来る限りのサポートをすることが望ましいです。
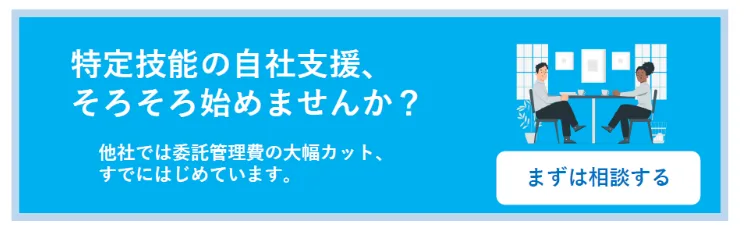
知っておきたい支援窓口・相談先一覧
病気やけがに限らず、生活や就労中のトラブル、言葉の壁による不安など、外国人を受け入れる企業にとっても、特定技能で働く外国人にとって「誰に相談したらいいかわからない」という状況は少なくありません。
ここでは、外国人向けの医療機関検索サービスや電話相談窓口、生活全般をサポートしてくれる機関を一覧で紹介します。
| カテゴリ | 名称・リンク | 内容概要 |
|---|---|---|
| 医療機関検索 | 外国人患者を受け入れる医療機関リスト(厚生労働省) →検索ページ | 外国人対応可能な医療機関を都道府県別に検索可能。通訳対応・診療科目なども確認可能。 |
| 医療機関検索(認証機関) | 外国人患者受入れ医療機関認証制度 JMIP → JMIP公式サイト | 厚労省が制度設計、一般財団法人日本医療教育財団が認証。多言語対応・診療体制が整った医療機関を全国から検索可能。 |
| 電話相談窓口(救急対応) | 救急安心センター(#7119) | ● 救急車を呼ぶべきか迷ったときの相談窓口 ● 看護師・医師が24時間365日対応(一部地域を除く) ● 電話:#7119 |
| 電話相談窓口(生活支援) | 法務省 出入国在留管理庁 外国人在留支援センター(FRESC)FRESC公式サイト | ● 在留外国人向けの多言語電話相談窓口● 特に技能実習生など生活に困っている人向けの支援● 在留・労働・医療等の相談に対応 |
特定技能の病気・けがの場合の通訳は?
言葉の壁がある状態で医療機関を受診するのは、大きなストレスとリスクを伴います。症状の説明がうまくできず、適切な治療が受けられないケースも少なくありません。特定技能外国人が病院に行く際には、下記の対応が一般的です。
①医療機関に常駐・派遣される医療通訳者を利用
一部の大病院や外国人受入れ医療機関では、多言語に対応できる通訳スタッフを配置しています。厚生労働のJMIP認証の医療機関では対応しているケースが多いため、事前に確認してリストアップしておくと安心です。医療機関についてはこちらから検索・確認が可能です。
②電話・タブレットを使った遠隔通訳サービスを利用
通訳スタッフがいない医療機関でも、タブレットや電話を通じて通訳を行う「遠隔医療通訳」を利用することによってどの医療機関でも通院することができます。通訳サービスについては、下記の記事で詳しく解説しています。
③登録支援機関・受け入れ企業による通訳サポート
受け入れ企業や登録支援機関が医療機関への同行・通訳を行う場合もあります。注意点として、医療通訳は本人の健康に直結する内容を扱います。万が一の際に責任を取れるかどうかわからないため友人・同僚による通訳だけで済ませるのは避けた方がよいでしょう。特に症状や処置内容、薬の副作用などの説明には専門的な通訳が必要です。
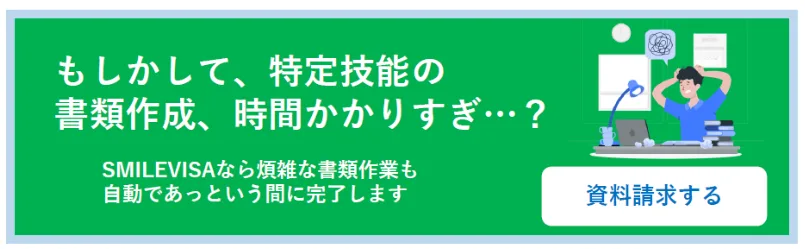
実際にあったケース集|特定技能外国人と体調不良・疾病対応の実例

制度は理解していても、実際にどんな問題が起きるのかを知っておくことは非常に重要です。ここでは、特定技能で来日している外国人が病気やけがをした際に実際に起きた事例についていくつかご紹介します。
(1) コロナ感染症で出勤停止・労災認定されたケース(飲食業)
- 背景:飲食店で勤務していた特定技能外国人が新型コロナウイルスに感染。保健所の指導により出勤停止となった。
- 対応内容:業務中や通勤中の感染が疑われたため、労災保険の申請を行い、労災認定が下りた。
- ポイント:コロナ感染も状況により労災認定の対象になる。企業は速やかに労働基準監督署に相談し、本人と連携して申請を進める必要がある。
詳しくは厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)にて確認が可能です。
(2) 妊娠によるつわりで時短勤務に変更したケース(製造業)
- 背景:特定技能外国人が妊娠し、つわりが重くなったことで、通常業務の継続が困難に。
- 対応内容:会社と相談し、約3~4か月間の時短勤務に変更。本人の健康と胎児への影響に配慮した就労体制が取られた。
- ポイント:1週間の所定労働時間が30時間未満になる場合は、雇用条件変更の随時届出が必要。
また、妊娠・出産に関する制度を本人に案内することも重要。
特定技能の妊娠出産に関しては、詳しくは下記の記事で解説しています。
(3) 夜勤・日勤の交互勤務で体調不良に(介護・製造系など)
- 背景:夜勤と日勤が頻繁に交互に組まれた勤務シフトにより、特定技能外国人が体調を崩す。
- 対応内容:あるケースではシフト調整によって継続勤務が可能になったが、別のケースでは退職につながった。
- ポイント:不規則な勤務は日本人でも負担が大きく、外国人には特に体調管理が難しい。
継続的な健康チェックと勤務形態の見直しを企業側が定期的に行うことが重要。
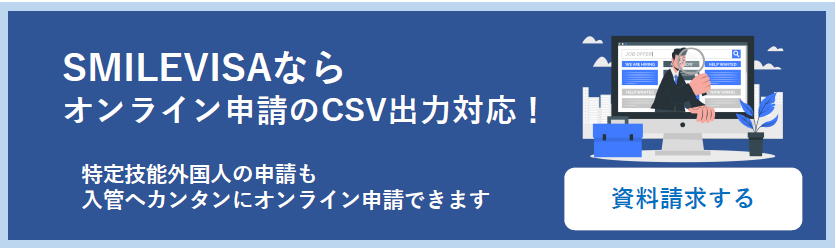
よくある質問(Q&A)
Q1. 働けなくなった場合、在留資格はすぐに取り消されますか?
A. 原則として「就労できる状態」が在留資格維持の条件ですが、すぐに取り消されるわけではありません。出入国在留管理局に相談し、必要であれば在留資格の変更や延長を申請することで対応できるケースもあります。
Q2. 雇用主が病気の外国人を解雇することはできますか?
A. 労働基準法上、病気やけがを理由に即時解雇することはできません。ただし、就労が長期間困難な場合は雇用契約終了の可能性もあるため、慎重な対応が求められます。特定技能外国人の意思を尊重し、適切な対応を心がけましょう。
Q3. 特定技能外国人を受け入れ予定です。医療に関して、備えておくべきことはありますか?
A. 自治体によっては医療通訳の派遣や多言語の医療情報を提供している場合があります。また、民間のオンライン通訳サービスも利用できます。外国人に対応可能な病院情報を事前に確認・登録しておくと安心です。また、最近では特定技能外国人向けの医療サポートサービスなども提供されているため、検討するとよいでしょう。
特定技能外国人の医療に関する無料セミナーはこちら
特定技能外国人を受け入れている企業の皆さま向けに、医療制度の基礎知識や、実際のトラブル事例、対応のポイントを学べる無料セミナーを開催しています。
「外国人が病気になったとき、どこに連れていけばいいの?」「通訳はどうする?」「入管への手続きは何が必要?」といった現場の疑問に、専門家がわかりやすく解説します。現在、無料オンデマンド配信中となりますので下記よりお申込みください!
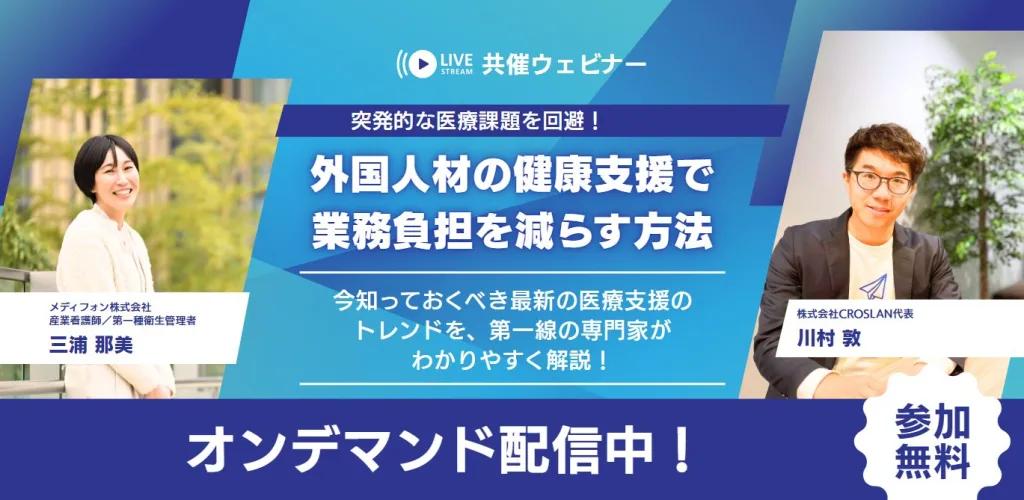
まとめ
特定技能で働く外国人にとって、病気やけがは誰にでも起こりうる現実です。今回ご紹介したように、症状や状況に応じた制度の活用や、相談窓口・医療機関の事前把握があれば、予期せぬトラブルを防ぎ、安心して働き続けることができます。
受け入れ企業の担当者は、「もしもの時」に備えて正しい知識をもち、実際の対応につなげられるよう、日ごろから準備をしておきましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。