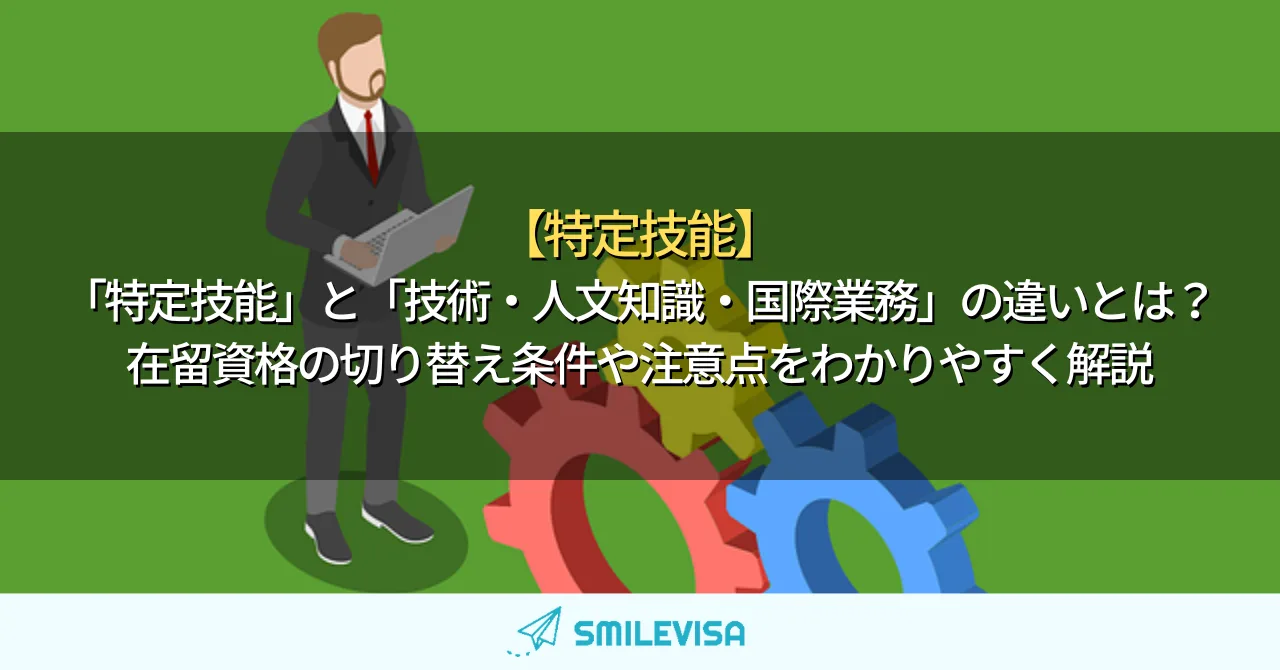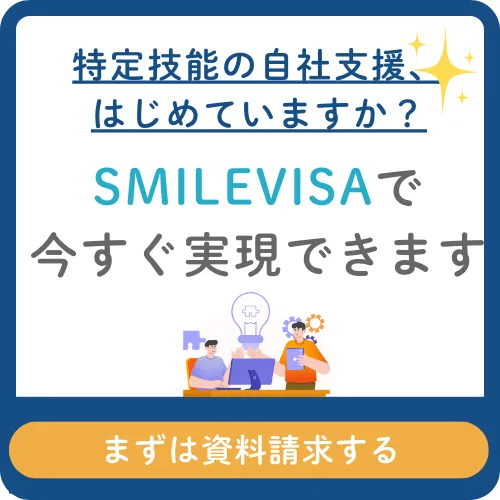目次
みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
雇用している特定技能外国人の業務内容の変更などに伴い、在留資格を切り替えたいという企業も少なくありません。特定技能外国人の在留資格を「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」に切り替えることは、制度として認められています。
しかしながら、切り替える場合には様々な要件があり、必要な書類を提出することが義務付けられています。今回は、特定技能から在留資格「技術・人文知識・国際業務」への切り替え方法について詳しく解説していきます。
また、記事の最後にて特定技能・必要書類の一覧を無料でダウンロードいただけます。
特定技能と技術・人文知識・国際業務の違いとは?
「特定技能」は、一定の専門的技能を持つ外国人が人手不足の業種で働けるように設けられた在留資格で、介護・外食・建設など14分野に限定されています。一方「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、企業での事務職やエンジニア職など、より専門性の高い知識やスキルが求められる職種が対象となります。
| 項目 | 特定技能(1号) | 技術・人文知識・国際業務(技人国) |
|---|---|---|
| 在留資格の目的 | 人手不足分野での労働力確保 | 専門的知識・スキルを活かした職業での就労 |
| 対象職種 | 介護・外食・建設など16分野の特定業種 | エンジニア・事務・通訳・マーケティングなど |
| 学歴要件 | 不要(技能試験・日本語試験合格が必要) | 大卒または専門学校卒が原則(職務との関連が必要) |
| 就労内容 | 実務中心 | 専門的・知識系業務(オフィスワーク・企画・分析・翻訳など) |
| 在留期間 | 最長5年(更新制) ※特定技能2号は更新すれば期限なし。 | 更新により期限なし。長期在留や永住につながる可能性あり |
| 家族の帯同 | 不可 ※特定技能2号なら可能 | 可能(配偶者・子どもを呼べる) |
| 日本語能力要件 | JLPT N4レベル以上が基本 | 実務に応じた日本語力(N2〜N1程度が目安) |
| 永住や転職の可能性 | 1号では永住不可 2号は永住の可能性あり ※いずれも転職は可能 | 長期的に働け、転職は自由・永住も視野に入る |
| 企業側の負担 | 比較的高い(特定技能1号については支援計画の策定・実施の義務あり) | 日本人とほぼ同等 |
このように、特定技能と技術・人文知識・国際業務においては様々な面で違いがあります。この違いを理解し、企業側はどのような人材を受け入れるか考慮する必要があります。
特定技能から「技術・人文知識・国際業務」への切り替えは可能?

特定技能外国人の在留資格を「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」に切り替えることは可能ですが、無条件で切り替えられるわけではありません。
まず、「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との継続的な契約に基づいていることが前提となります。その上で、該当する活動内容としては、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と出入国在留管理庁で定められています。(※在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) 「この在留資格に該当する活動」より抜粋)
少しややこしい表現に感じますが、簡単に言えば、「特定の分野で専門的な知識や技術を要し、外国の文化を理解する必要のある業務」であればよい、ということになります。「技術・人文知識・国際業務」には、特定技能よりも、学術的な知識や高い専門性、技術性や外国文化に対する感受性が求められることになります。
具体的な職業としては、機械工学等の技術者や通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が該当します。
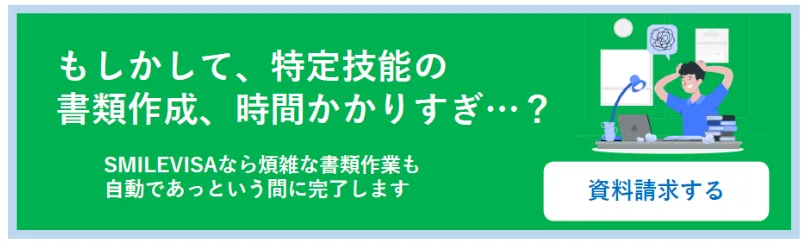
例えば日本語学校でベトナムやネパール国籍の学生を募集するためのマーケティングスタッフなどは、日本語と現地語の高い語学力と、文化の理解が必要不可欠です。また、英会話学校の教師などはネイティブスピーカーであることで、英語のほかにも現地の文化を教えるなど、外国人である必要がある職業と言えるでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」には、法務省が定める基準も設けられています。「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」に従事しようとする場合、大学や専修学校において、従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること、もしくは10年以上の実務経験があることが必要です。基本的には大卒や専門学校卒である必要があり、さらに就職しようとする分野で学位を取得している必要もあります。
そのため、特定技能外国人が「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合は難易度が高いと言えるでしょう。例えばですが、業種にもよりますが、特定技能外国人が本国に帰国し、習得した技術を広めているケースや、日本にいる場合は企業内で技能実習生や特定技能外国人の指導をしているケースなどでは可能性があります。しかし、日本語能力も要件が厳しくなり、最低でもJLPTのN2以上であることが求められるでしょう。
特定技能からの切り替えに関しては、実際に申請を出してみるまではわからない…ということになりますので、特定技能外国人からの切り替えを検討している場合は、該当する外国人が条件などをクリアしているのか出入国在留管理庁へ直接問い合わせる必要があります。
詳しくはこちらより→ 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
特定技能から技術・人文知識・国際業務へ切り替えた実例

ここでは、実際に特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への切り替えに成功したケースとポイントをご紹介します。
例①外食分野での切り替え例
外国人社員が特定技能(外食)で入社し、まじめに勤務していたため、社内の海外マーケティング部門に登用を検討。日本語能力はN2、母国ではビジネス系の専門学校を卒業しており、将来的には複数の店舗にてマネジメントや海外進出マーケティングを担当する人材として、技人国で求められる「国際業務」に該当する業務内容(販促企画・翻訳・調査)を明確に整理して申請。
外食業務からの切り替えだったため、店長といった役職では在留資格がおりないため、キャリアアッププランとして将来的には複数店舗の統括、数値管理、店舗間の運営品質向上支援、外国人採用・教育制度の整備、本社との調整・レポーティング、インバウンド戦略、研修プログラム構築などの主に本社での職務を想定し、就労することを説明。結果、無事に技人国に変更許可が下り、今では正社員として社内の外国人向け施策をリードする業務に従事。
⇒ポイントとして、店長レベルの店舗管理や、現場での就労だと技術・人文知識・国際業務への切り替えは難しいため、本社での勤務を想定した業務内容を丁寧に説明したことで切り替えに成功✅
【例②工業製品製造分野での切り替え例】
元々は、インドネシア人の特定技能外国人として工業製品製造分野のキャリアを積み、現場リーダーとして生産・品質管理に幅広く携わっていました。母国の大学で機械加工を学んでおり、自社の品質基準や製造工程にも深い理解があることから、技術・人文知識・国際業務(技人国)への切り替えを検討。
将来的には技能実習生への技術指導や、機械のオペレーターや加工機械のプログラミング、生産工程の改善、品質管理データの分析、現場教育制度の構築など、本社機能に関わる業務への登用を想定。
特定技能では「作業者」としての業務にとどまるが、切り替えにあたっては「専門知識を要する技術指導・品質管理・社内教育業務」など、上流業務への移行を丁寧に設計・説明。結果、本人の学歴・実務経験・日本語能力・貢献実績が評価され、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可され、現在は品質管理と人材育成の中心メンバーとして活躍中。
⇒ポイントとして、「技能実習や特定技能での現場経験+大学での専門知識+本社レベルでの職務構想」の3点を具体的に示したことで、切り替え成功につながった事例✅
特定技能から在留資格「技術・人文知識・国際業務」への切り替え方法とは?
特定技能から在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ切り替える場合、特定技能受入れ機関に応じて、4つのカテゴリーに区分されます。カテゴリー別に必要な書類が異なるため、どのカテゴリーに当てはまるのか確認しましょう。
在留資格を切り替える場合、特定技能受入れ機関は4つのカテゴリーに区分される
まず、在留資格「特定技能」から、「技術・人文知識・国際業務」へ切り替える場合、4つのカテゴリーはどのようなものなのか見ていきましょう。
4つのカテゴリーは、下記の表の通りに区分されます。
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
区分 | 日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本又は外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人 ・イノベーション創出企業(詳細 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 ・一定の条件を満たす企業等(詳細 一定の条件を満たす企業等について ) | ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) (→前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が1,000万円未満の団体・個人) | ・カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人 |
受入れ企業が、このカテゴリーのどこに分類されるかで必要な書類が変わってきます。そのため、まずはどこのカテゴリーなのかをチェックしましょう。
在留資格変更の際、カテゴリー別の必要な書類
4つのカテゴリーが分かったところで、まずは共通で提出する必要のあるは下記の通りです。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
- パスポート及び在留カード 提示
そのほか、カテゴリーごとで提出するべき書類については出入国在留管理庁の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に記載がありますので、こちらを確認して揃えて提出となります。
在留資格を切り替えてそのまま雇用する場合でも随時届け出は必要?
在留資格を切り替えてそのまま雇用を継続する場合でも、随時届出は必要です。
在留資格 「特定技能」でなくなる見込みがたった場合は、特定技能雇用契約が終了するため、受入れ困難に係る届出(詳しくはこちらの記事で解説)を提出しましょう。
在留資格「特定技能」でなくなった後には、特定技能雇用契約終了に係る届出も必要です。
登録支援機関に対して支援の全部の実施を委託していた場合、支援委託契約終了の届出も必要となります。
「切り替え」を検討する際の注意点
在留資格を切り替えて活動する場合、速やかな申請が義務付けられています。
本来の在留資格に基づいた活動をしていない場合は、在留資格が取り消されてしまうおそれがあります。例えば、まだ新しい在留資格に切り替わっていないうちから新しい在留資格で定められた就労を開始させるのはNGです。
また、申請書類を提出するのが申請人本人以外の場合、提出する方の身分証明書や申請取次者証明書の提示が必要となります。提出の際には、忘れないようにしましょう。
特定技能と技術・人文知識・国際業務のよくある質問(FAQ)
Q1. 特定技能で働いていた職場と同じ企業で、技人国に切り替えることはできますか?
A. 可能ですが、職務内容が「専門性のある業務」に変わる必要があります(例:通訳・事務・技術職など)。これまでと同じ特定技能の業務では切り替えができないため注意しましょう。
Q2. 特定技能と技術・人文知識・国際業務、どちらが永住に有利ですか?
A. 技人国は在留期間の上限がないため、更新を続ければ永住申請には有利です。しかしながら、特定技能2号に移行した場合については、働き続ける限りは更新が無期限で可能なため永住権の取得ができます。そのため、特定技能1号を除き、特定技能2号と技術・人文知識・国際業務では永住権の可能性としてはあまり差がありません。
Q3. 技人国での就労中に転職は可能ですか?
A. はい、転職は可能ですが、転職先の業務内容も在留資格の要件に合致している必要があります。そのため転職先の受け入れ企業での就労内容が適切なものかは事前に確認する必要があるでしょう。
特定技能・必要書類の一覧の無料ダウンロードはこちら
特定技能外国人の受け入れに際する必要書類について詳しく知りたい受け入れ企業のためのガイドです。受け入れ企業が一定の事業規模に該当する場合と該当しない場合の必要書類や、注意事項などついて、抑えるべきポイントが一目瞭然です。
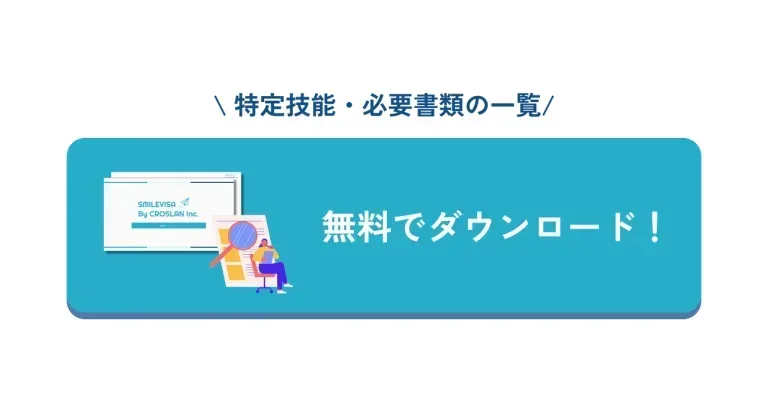
在留資格を切り替える場合は速やかに必要な書類の提出を!
今回は、特定技能から在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ切り替え方法について解説しました。
特定技能から在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ切り替えた場合は、必要な書類を速やかに提出する義務があります。提出を怠ってしまうと、在留資格が取り消される可能性があります。特定技能機関がどのカテゴリーに区分されるのかを十分に確認した上で、提出する書類を用意しましょう。
また、特定技能の採用と在留資格に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!
【詳細&お申込みはこちらから】

※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
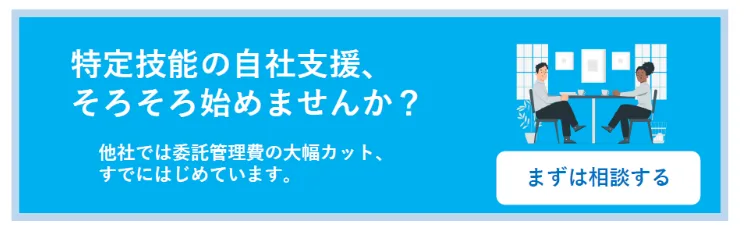
※本記事は現時点(2025年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。