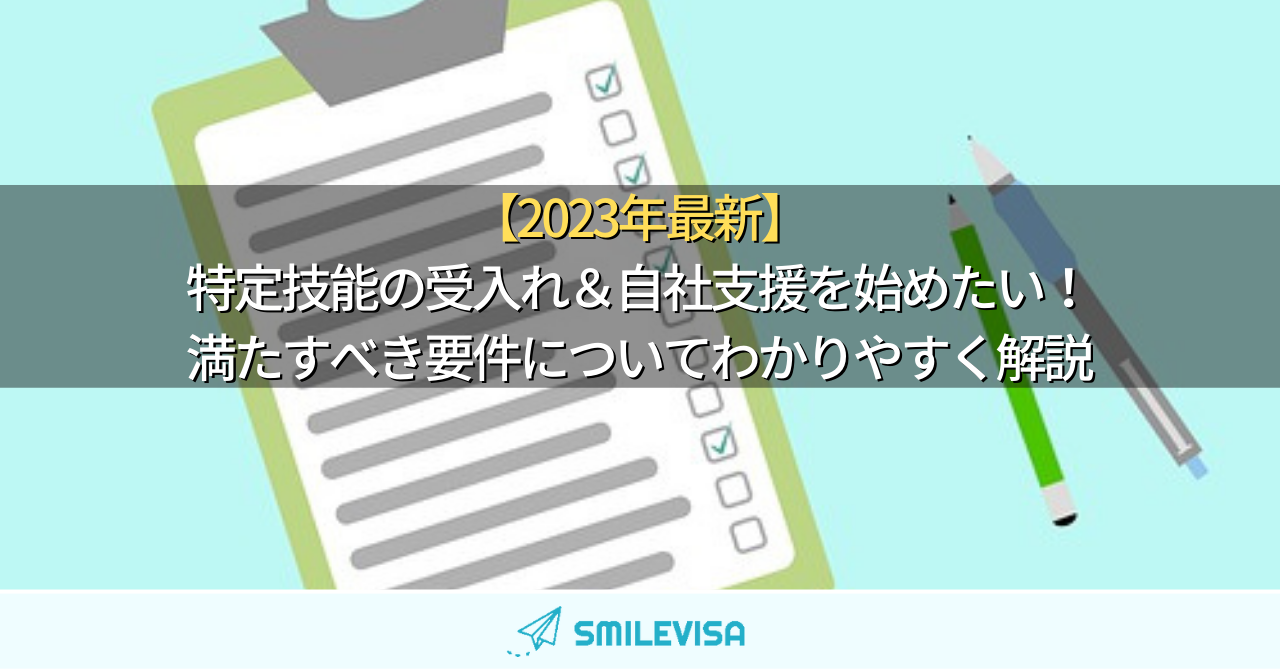目次
- そもそも特定技能制度とは?
- ①特定技能外国人を受け入れるための要件(条件)は?
- (1)労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守しているかどうか
- (2)非自発的離職者が発生していないか
- (3)行方不明者を発生させていないか
- (4)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由に当てはまるかどうか
- (6)出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないか
- (7)暴力団関係者ではないか
- (8)特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性があるかどうか
- (9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成や保存ができるかどうか
- (10)保証金の徴収・違約金契約等をしていないか
- (11)支援に要する費用を外国人に負担させていないか
- (12)派遣形態による受入れの条件を満たしているか
- (13)労災保険法に係る措置等は適切かどうか
- (14)特定技能雇用契約継続履行体制があるか
- (15)報酬の口座振込み等が適切かどうか
- (16)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合するかどうか
- ②特定技能外国人を自社支援で受け入れるための要件(条件)は?
- 定められた要件に沿って、特定技能の受入れを行いましょう!
みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
特定技能外国人について、興味はあるけれどどうやって受け入れたらいいのかわからない・・・。特定技能外国人をゆくゆくは自社支援でやっていきたいけれど、そのための条件などはあるの?といった疑問を持つ受入れ企業の担当者の方は多いですよね。
今回の記事では、
①特定技能外国人を受け入れるための要件(条件)
②特定技能外国人を自社支援で受け入れるための要件(条件)
この2つについて、わかりやすく解説していきます!
そもそも特定技能制度とは?

「特定技能」という制度については聞いたことがあるけれども、実際には特定技能制度とは?というところからご説明したいと思います。
現在、日本においては中小企業をはじめとした人手不足が年々深刻化しており、このままでは人材不足による経済や社会の持続が困難になることが予想されています。そこで、日本政府は、生産性向上や国内人材確保のため「特定技能」制度を2019年に創出しました。
人材を確保することがどうしても難しい12産業の分野において雇用が可能となったのが、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」、つまりこれが、「特定技能外国人」となります。
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。この2つの違いについては、こちらの記事「特定技能2号とは?手続きの方法や1号との違いについて解説!」で詳しく解説しています。
ポイントとなる点としては、「特定技能1号」で在留する外国人に対しては受入れ企業もしくは登
録支援機関による支援が必要です。一方、特定技能2号については、支援の対象外とされています。
つまり、特定技能外国人1号を受け入れる場合、受入れ企業は支援の実施について、登録支援機関へ委託するか、もしくは自社で支援を行うかを選ぶことができるということです。
登録支援機関へ委託する場合と自社支援のメリット・デメリットについてはこちらの記事「【どっちがお得!?】特定技能の自社支援VS登録支援機関へ委託のメリット・デメリットを比較してみた」でもご紹介しています。
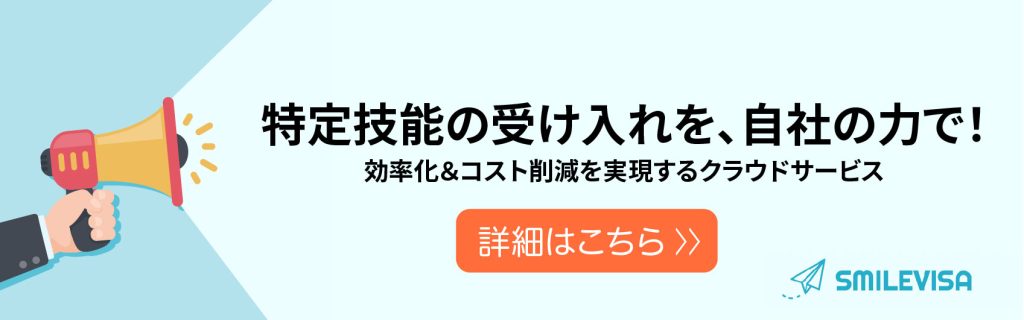
①特定技能外国人を受け入れるための要件(条件)は?

そもそも、特定技能外国人自体を受け入れたい!と思っても、実際に受け入れ企業が出入国在留管理庁から指定された条件を満たしていないと、特定技能外国人の受入れ自体ができません。
まず第一に、特定技能の受入れができるのは下記、12分野です。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
その上で、出入国在留管理庁では、特定技能外国人がどのような要件(条件)を出しているのか、下記チェックしてみましょう!
(1)労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守しているかどうか
特定技能の受入れ企業は、労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることが必要となります。こちらは簡単に言えば、労働基準法を守り、社会保険や国税など定められた決まりに沿って税金などを納めていれば問題はありません。
(2)非自発的離職者が発生していないか
そもそも特定技能とは、深刻な人手不足の解消を目的とした制度です。そのため、特定技能の受入れ企業が現在雇用している従業員を会社の都合で解雇し、その補填として外国人を雇用することはNGとなります。
したがって、 特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も、会社都合でリストラなどを行っていないことが求められます。
(3)行方不明者を発生させていないか
特定技能の受入れ企業は、受入れ企業側の責任によって雇用する外国人について行方不明者を発生させている場合には、受け入れ態勢が十分でないとみなされることになります。そのため、特定技能外国人と雇用契約締結の日から前1年以内、そして契約締結後に行方不明者を発生させていないことが求められます。
(4)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由に当てはまるかどうか
特定技能外国人を受け入れる企業は、過去に法令違反があった場合は受け入れができません。具体的には下記の通りです。
① 禁錮以上の刑に処せられた者
② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
※いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」が対象です。
さらに、技能実習生を受け入れている企業が、実習認定の取消しを受けたことがある場合は、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)は、特定技能所属機関になることはできません。
過去に実習認定の取り消しを受けてから5年は特定技能外国人を受け入れることはできませんので、注意しましょう。
(6)出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないか
特定技能雇用契約の締結の日から前5年以内もしくはその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った場合は、欠格事由に該当し、特定技能所属機間になることはできません。
こちらは様々なケースが考えられますが、出入国の際に違法な行為をした、書類の作成で虚偽を行ったなども該当します。こちらは個別のケースに応じて、判断されることとなりますので不安な場合は出入国在留管理庁へ問い合わせてみましょう。
(7)暴力団関係者ではないか
特定技能を受け入れる企業は、暴力団関係者ではないことが求められます。
こちらは、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)及びその役員が暴力団員等であったり、暴力団員等がその企業活動を支配する場合は受け入れができません。
(8)特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性があるかどうか
特定技能を受け入れる企業は、特定技能を受け入れるための適性が必要です。具体的には、以下の通りです。
① 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない場合
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号に該当する者
こちらは、業務を行う上で精神機能に障害がないか、破産手続きを受けている最中である場合や、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は受け入れ企業になることはできません。
(9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成や保存ができるかどうか
特定技能を受け入れる企業は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に保管しておくことが求められます。こちらは紙の書類でも、データでも問題ありません。
(10)保証金の徴収・違約金契約等をしていないか
特定技能の受け入れ機関は、特定技能外国人(もしくはその親族等)が、特定技能外国人として日本へ来日する際に、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結させられていないことを確認する必要があります。
例えばですが、受入れ企業はもちろんのこと、登録支援機関や職業紹介事業者、海外の仲介事業者などから不当な保証金や、財産の管理をなされていないことを確認します。具体的には、失踪防止のための違約金を課すことや、休日に外出したり作業時間中にトイレ等で離席することなどを禁じ、破った場合は罰則金を課すことなどが含まれます。
(11)支援に要する費用を外国人に負担させていないか
特定技能外国人に対し、受入れ企業は支援にかかった費用(義務的支援に限る)について、負担させることはできません。
この費用とは、主に登録支援機関へ委託した場合にかかる月額の管理費になります。この費用は毎月かかってくる費用となりますが、必ず受け入れ機関が負担しなくてはなりません。
(12)派遣形態による受入れの条件を満たしているか
こちらは農業や漁業などの派遣形態を認める分野のみですが、特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることが必要です。
また、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合も可能です。
派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様に、労働基準法や、社会保険及び租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことが求められます。
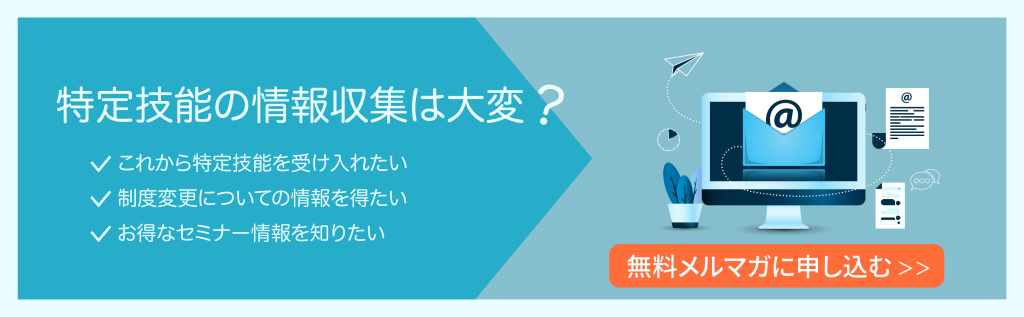
(13)労災保険法に係る措置等は適切かどうか
特定技能外国人に対して、受入れ企業は労働者災害補償保険の適用を確保する必要があります。受入れ企業が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に行っている必要があります。
(14)特定技能雇用契約継続履行体制があるか
特定技能の受入れ企業は、安定した就労活動を確保する必要があります。特定技能雇用契約を継続して履行する体制があることが求められ、事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤が必要です。
(15)報酬の口座振込み等が適切かどうか
受入れ企業は、特定技能外国人に対する報酬の支払を確実かつ適正なものにしなくてはなりません。外国人に対し、報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上、当該外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振込み等により行う必要があります。
万が一、預貯金口座への振込み以外の支払方法(現金で支払い等)をする場合は、出入国在留管理庁へ支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、確認を受ける必要があります。
(16)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合するかどうか
このほか、それぞれの分野ごとにも条件が出されている場合がます。その条件についてはこちらの出入国在留管理庁「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」より確認ができます。
詳しくはこちらの出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」より詳細は確認ができます。
②特定技能外国人を自社支援で受け入れるための要件(条件)は?

ここまで特定技能外国人を受け入れることができるかどうかの条件をご紹介しました。続いては、特定技能外国人を自社支援で受け入れることができるかどうかの要件(条件)についてご紹介します
(1)中長期在留者(外国人)の受入れ実績などがあるかどうか
まず第一に、特定技能外国人を自社支援する受入れ企業は、下記の3つのいずれかの条件を満たす必要があります。
- 過去2年間に中長期在留者の受入れもしくは、管理を適正に行った実績があること。かつ、役員もしくは職員の中から、特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(担当者)を事業所ごとに1名以上選任していること。
- 受け入れ企業の役員もしくは職員の中で、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある人の中から支援責任者(担当者)を事業ごとに1名以上選任していること。
- ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができるとして、出入国在留管理庁長官が認めるもの。
※中長期在留者とは、就労資格を持った外国人を指します。(技術・人文・国際業務や、技能実習生が含まれます。一方、留学生や永住者などは含まれません)
また、自社支援する場合は、役員か職員の中から、特定技能外国人の支援計画の実施の担当者を用意する必要があります。この担当者は、「支援責任者(担当者)」と呼ばれます。
この支援責任者(担当者)については、事業所ごとに1名以上置くとされていますが、飲食店や介護事業所などでは難しい場合があるため、その場合は本社に1名在籍させ、事業所をローテーションする形でも問題ありません。
つまり、これまで過去2年間の間に、特定技能の支援を登録支援機関に委託していたり、技術・人文・国際業務などで雇用した経験がある企業については基準を満たしているということになります。不安な場合は、出入国在留管理庁へ問い合わせるか、SMILEVISAのお問合せからもご相談が可能です。
(2)十分に理解できる言語による支援体制が用意できるか
特定技能外国人が、日本語のみで生活や業務を行うことに支障がある場合は、外国人が十分に理解することができる言語によって支援を行う体制が必要です。
通訳翻訳のできる担当者を確保することが求められますが、オンライン通訳翻訳サービスなどの利用でも問題ありません。しかし、外国人が通訳・翻訳が必要な際にすぐに手配できることが求められます。
(3)支援の実施状況に係る文書の作成・保管ができるかどうか
受入れ企業は、特定技能外国人の支援状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上は事業所に保管しておく必要があります。
(4)支援の中立性が確保的出来るかどうか
特定技能外国人を支援する「支援責任者(担当者)」は、中立的な立場にある必要があります。
具体的には、特定技能外国人を監督する立場にないこと、そして特定技能受け入れ機関と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であることが求められます。
例えば、飲食店で特定技能外国人受け入れた際に、その外国人の働く事業所の店長など、外国人を監督・評価する立場である場合は、支援責任(担当)者になることはできません。
総務や人事などの別の部署の従業員が支援責任者(担当者)になる必要があります。
(5)支援実施義務の不履行がないかどうか
特定技能の自社支援をする場合は、特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、特定技能外国人支援を怠ったことがないことが求められます。
こちらは以前受け入れた外国人も含め、定められた支援を行っていれば特に問題はありません。万が一怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、自社支援が難しくなります。
(6)定期的な面談の実施に関するもの
特定技能の受入れ企業は支援援責任者(支援担当者)が特定技能雇用契約の当事者である外国と、その監督する立場にある者と定期的な面談を実施することが必要です。こちらは定期面談と呼ばれるもので、最低でも3か月に1回は行う必要があります。
定期面談についてはこちらの記事「【特定技能】特定技能外国人との定期面談とは?行う時期や報告書の作成方法まで解説!」で詳しく解説しています。
(7)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合するか
このほか、それぞれの分野ごとにも条件が出されている場合があります。その条件についてはこちらの出入国在留管理庁「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」より確認ができます。
詳しくはこちらの出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」より詳細は確認ができます。
定められた要件に沿って、特定技能の受入れを行いましょう!
以上、特定技能の受入れをする際の要件(条件)と、特定技能の自社支援をする場合の受け入れ要件を紹介しました。
様々な決まりや要件がありますが、基本的には定められたルールに沿って適正に受け入れをしていればほとんど問題なくクリアできる内容になります。
SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様に対しては、自社支援を実現するためのサポートプランも充実しています。こちらよりお気軽にご相談ください!
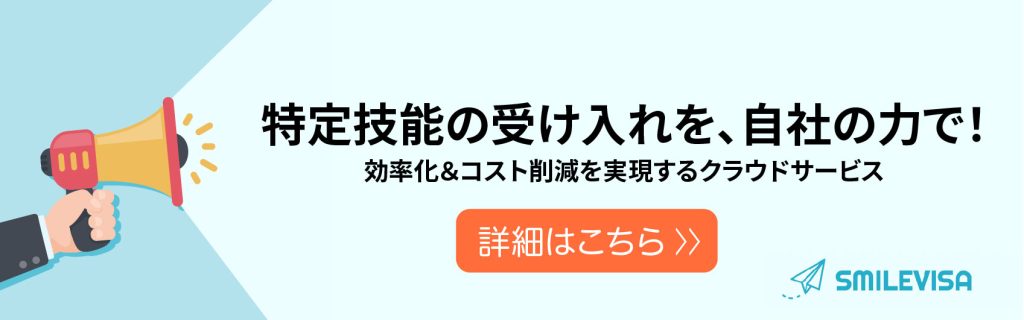
※本記事は現時点(2023年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。