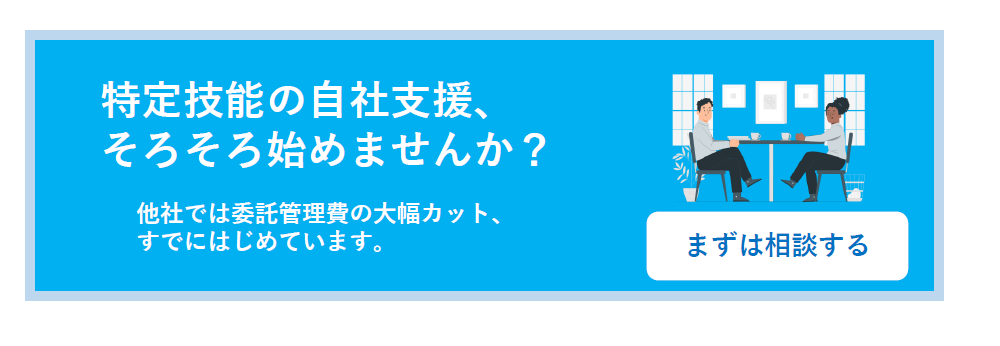目次
こんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の受け入れには、登録支援機関へ委託するか、自社で支援するかを選ぶことができます。これから自社支援に切り替えていきたい!となった場合に、出入国在留管理庁まで随時報告という形で、書類を提出する必要があります。
これから自社支援に切り替える際に、どのような報告を行えばよいのかわかりやすく解説していきます。
そもそも特定技能の自社支援とは?
自社支援とは、特定技能外国人に対する支援を、登録支援機関に頼らずに受入れ企業である自分達ですることです。特定技能外国人に対して支援が必要な項目として、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 事前ガイダンス
- 住民票の届出
- 銀行口座の開設手続き
- 日本語学習機会の提供
などが対象となりますが、具体的に発生する業務についてはこちらの記事で確認ができます。
自社支援に切り替えることで手続きや支援に時間がかかるというデメリットがありますが、一方で以下のようなメリットが発生します。
自社支援のメリット
- 外部に委託する費用をカットできる!
- 自社で外国人受け入れのノウハウを蓄積できる
- 外国人とのコミュニケーションを密にとれる
特に、外部に委託する費用をカットできるのは大きいです。特定技能外国人の管理委託にかかるコストは1名あたり月2.5万円が平均となっており、年間で見るとその費用は30万円にもなります。
今後外国人採用が増えていく中で、自社で受け入れることができれば大幅にコストカットできるようになります。
メリットデメリットに関してはこちらの記事詳しく説明しています。
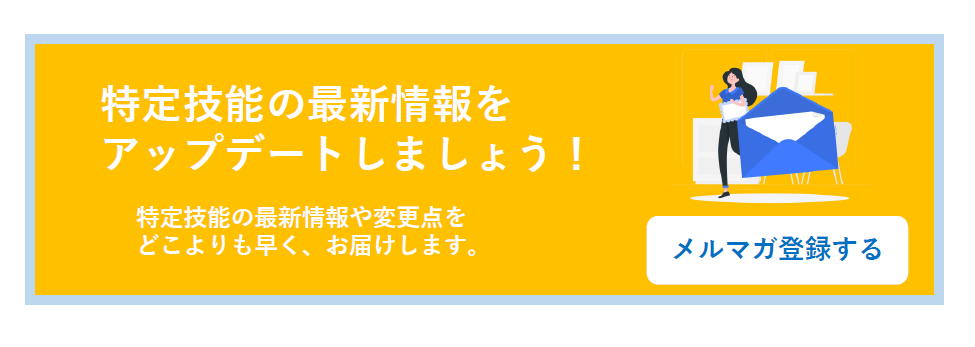
企業が自社支援を始めるための条件とは?

自社支援に切り替えよう!と思ったらまずは自社がきちんと要件を満たせているのかを確認します。自社支援を行うために、具体的に満たす必要がある要件については、下記の記事にて詳しく解説しています。
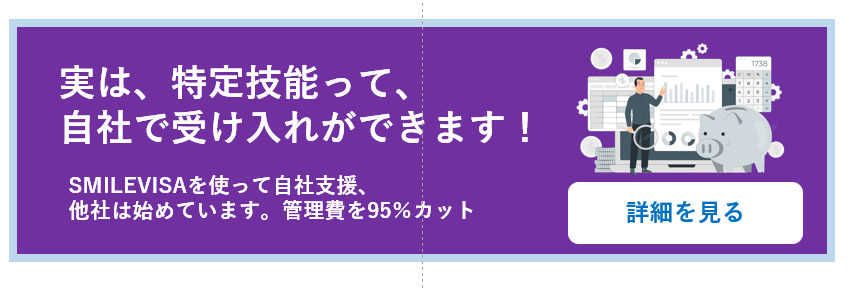
企業が自社支援に切り替える際の手続き・書類は?

自社支援を行うことができる要件を満たしていることを確認できたら、いよいよ手続を行なっていきます。必要書類と届出先は下記の通りです。
出入国在留管理庁へ提出する必要書類
下記の様式については、こちら在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)よりダウンロードが可能です。
①支援計画の変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
自社で支援を始めるにあたって支援計画が変更されるため、届出が必要になります。
※対象者が複数いる場合は、別紙 参考様式第3-2号を併せて記入し、届け出を行います。
②新しい支援計画書(参考様式第1−17)
変更後の支援計画の内容を証明するために必要です。
③特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(参考様式3-3-2)
自社支援に切り替えた場合、これまでの登録支援機関との契約が終了しますので、参考様式第3-3-2号(契約の終了した又は新たに締結した場合)を提出し、支援委託が終了したことも報告します。
※対象者が複数いる場合は、別紙(参考様式3−3号)を合わせて利用し、届出を行います。
④特定技能所属機関概要書(参考様式第1−11ー1号)
特定技能所属機関=外国人を受け入れる企業のことです。受け入れる企業の概要を知らせるためにこちらを提出します。
⑤受け入れ企業の組織図
こちらは政府の運用要領には書かれていませんが、”特定技能の支援担当者・責任者が外国人に対して業務上の指示をする権限を持つ者でないこと”を示すために、ほとんどのケースで組織図の提出が求められます。
組織図については、自由形式で簡素なものでも問題ありません。
また、受け入れ実績に応じて追加で提出する書類があります。
①過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある場合
→受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第1-11-2号)
②支援責任者及び支援担当者が過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有す場合
→生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第1-11-3号)および生活相談業務に従事したことおよび期間を証明する書類
③①と②以外にもこれらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができることを証明する場合
→任意の支援業務を適正に実施することを立証する資料および説明書
参考:出入国在留管理庁HP 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
届出先
窓口に持参する場合
受け入れ企業の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。
※該当する地方出入国在留管理官署が不明な場合は地方出入国在留管理官署、または外国人インフォメーションセンターに問い合わせることができます。
郵送による場合
身分を証する文書等の写しを同封の上、受け入れ企業の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付します。その際、封筒の表面に朱書きで、「特定技能届出書在中」と記載します。
インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届け出を行います。事前に利用者情報登録を行う必要があります。
※利用者情報登録はオンラインで手続きが可能です
相談窓口
分からないことがあった場合は、地方出入国在留管理官署、または外国人インフォメーションセンターに問い合わせることができます。
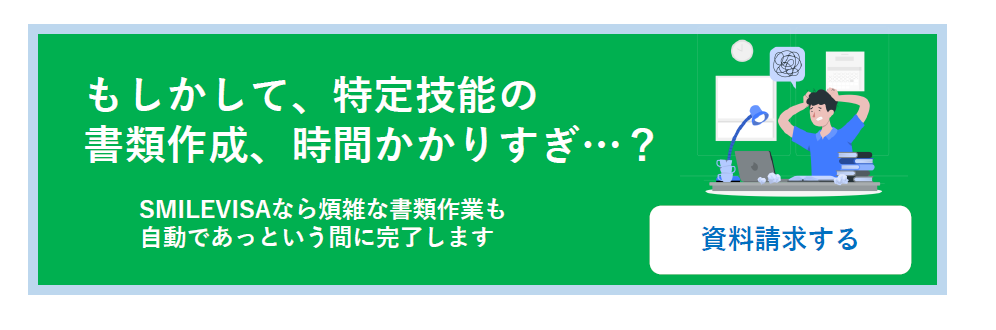
特定技能の自社支援を効率よく行うために
今回は特定技能を自社支援に切り替える方法を解説しました。自社支援に切り替える場合は、これまで行なう必要のなかった手続きが発生してしまう一方、外国人とより密にコミュニケーションを取れる点や、委託費用を抑えられる点で大きなメリットがありますが、書類の提出などは期限内に必ず終わらせるようにしましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!