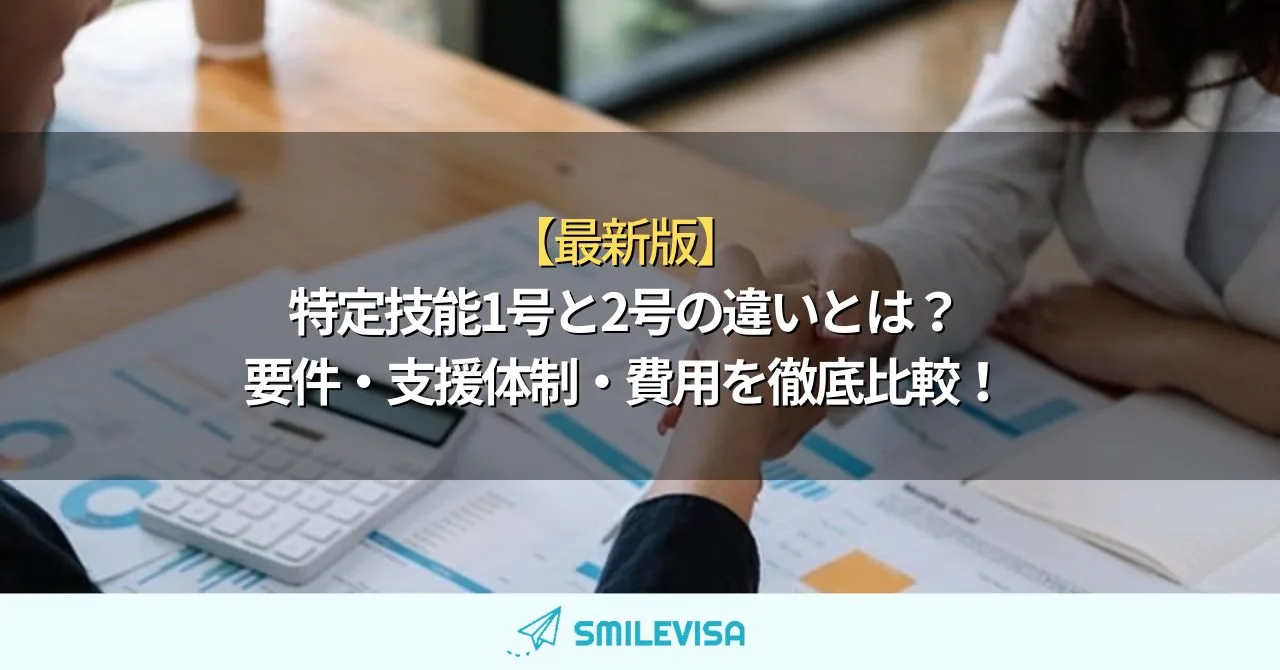目次
みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
近年、日本での外国人労働者の受け入れが進む中、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの在留資格の違いが注目されています。どちらも就労を目的とした制度ですが、求められるスキルや在留期間、受けられる支援内容、手続きの費用などに大きな違いがあります。
本記事では、最新の制度情報(2025年版)をもとに、特定技能1号と2号の違いをわかりやすく比較し、それぞれの特徴を解説します。これから外国人雇用を検討している企業担当者や、制度の理解を深めたい方は必見です。
特定技能1号と2号の違いは?わかりやすく解説
特定技能1号と2号には、以下の8つの違いがあります。
- 出入国在留管理庁が定めた人材像
- 特定技能として在留できる期間
- 技能の習熟度
- 日本語能力の有無
- 家族の帯同の可否
- 支援が必要かどうか
- 受入れできる分野
- 試験の難易度
- 実務経験の有無
8つの違いについてわかりやすくまとめた表は下記の通りです。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 出入国在留管理庁が定めた技能水準 | 特定の産業分野で、相当程度の知識または経験を必要とする業務について働く人材。 ただちに一定程度の業務ができる水準。特定技能1号評価試験の合格が条件。 ※技能実習2号を修了した外国人は試験が免除される。 | 特定の産業分野で、熟練した技能が必要な業務について働く人材。 特定技能2号評価試験の合格、もしくは技能検定1級の取得が条件 監督・指導者として一定の実務経験が求められる ※分野によりますが、基本的に2年以上の実務経験が必要。 |
| 在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新により、最長5年間。 | 3年、1年または6か月ごとの更新により、無制限で在留可能。 また、特定技能2号を取得してから10年以上在留することで、永住権を取得できる可能性もあり。 |
| 日本語能力の水準は? | 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」 そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準。 ※技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除される。 | 特になし。 ※外食と漁業分野のみN3以上が必要 |
| 家族の帯同はできる? | 基本的に認められていない。 | 要件を満たせば可能。 ただし、帯同者は配偶者と子に限る。 ※兄弟や親の帯同は認められていない。 |
| 受入れ企業または登録支援機関の支援は必要? | 出入国在留管理庁へ支援計画を提出のうえ、支援が必要。 | 受入れ企業や登録支援機関の支援は不要。 |
| 受け入れできる分野は? | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 ※令和7年5月現在 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 ※令和7年5月現在 ※造船・舶用工業分野は溶接区分以外の業務区分が対象。 ※介護は専門の在留資格「介護」があるため対象外。 |
| 試験の難易度 | 比較的易しい | 比較的高い |
| 実務経験の有無 | 問われない | 現場での管理経験が問われる |
それでは特定技能1号と2号それぞれの特徴から、違いを詳しく見ていきましょう。
①出入国在留管理庁が定めた技能水準
特定技能1号に関しては、出入国在留管理庁の特定技能運用要領より「従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。」と記載されています。
一方特定技能2号に関しては、「従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。」と記載されています。
つまり、特定技能1号に関しては業務に必要な知識や経験があればOKですが、特定技能2号については熟練した技能が必要となるため、管理的な業務を行うことが想定されています。
特定技能1号の在留資格を申請するためには、特定技能1号評価試験の合格もしくは技能実習2号を良好に修了する必要があります。
特定技能2号においては、特定技能2号評価試験の合格、もしくは技能検定1級の取得が条件となっており、管理者、監督、指導者として一定の実務経験が求められています。分野にもよりますが、基本的に2年以上の実務経験が必要とされるため、ハードルは高いと言えるでしょう。
特定技能2号への移行要件については下記の記事でまとめています。
②特定技能として在留できる期間
特定技能1号に関しては在留期間が5年と定められており、5年を超えて日本へ在留することはできません。しかし、特定技能2号に関しては、更新さえすれば実質、無期限で在留資格を延長することが可能です。
いずれも在留資格の更新は定期的にありますが、特定技能2号に関しては更新を続ける限り日本に滞在することができ、かつ永住権の申請も可能になってくることから、日本人と同様に長期的に企業で働いてもらうことができます。
永住権についての詳細は、こちらの記事にて紹介しています。
③日本語能力の有無
特定技能1号は、「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」 そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と定められています。また、技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。
N4の日本語能力がどの程度であるかについては、日本語能力試験(JLPT)の公式サイトにて下記の通り記載されています。
基本的な日本語を理解することができる
読む(よむ)
・基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中なかでも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。
聞く(きく)
・日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。
つまり、特定技能1号においては日常生活や現場である程度日本語のやりとりができればOKという基準になります。
一方、特定技能2号には日本語能力についての定めは外食と漁業分野以外には特にありません。この2つの分野に関しては、外食は接客中に日本語を使用する機会が多いことや、漁業に関しては安全上の問題から適切に日本語でのコミュニケーションをとる必要があるため、N3以上が求められています。
しかしながら、特定技能2号外国人に関しては日本での滞在歴が長いことや、管理や監督経験が求められることから、全分野において相当の日本語能力があるものとみなされています。
④家族の帯同の可否
家族を日本に呼び寄せる場合は、特定技能1号については基本的には不可とされています。しかし、特定技能2号に関しては、要件を満たせば可能とされています。
注意点としては、帯同者は配偶者と子に限ります。本国の兄弟や親の帯同は認められていないません。
⑤支援が必要かどうか
特定技能1号を受け入れる際には、「支援計画書」を作成し、出入国在留管理庁へ提出、受け入れ後は企業が外国人の支援を行う必要があります。そのため、特定技能1号外国人の受け入れ企業は自社支援で外国人を支援するか、もしくは登録支援機関等へ支援を委託する必要がありました。
しかし、特定技能2号外国人に関しては、支援は不要とされています。これは特定技能2号外国人がすでに日本滞在が長期にわたることを想定し、特に生活するうえでサポートが必要ではないとされているためです。
とはいえ日本での仕事や生活で困ったことやサポートが必要な場合は出てくる可能性はあるため、その際は受け入れ企業が適切な支援をすることが想定されますが、特定技能1号のように支援計画を提出したり、支援が義務であることはなくなります。
特定技能1号は支援が義務であったため、支援業務を管理団体へ委託している場合は費用がかかりますが、特定技能2号に関しては不要となります。しかし、特定技能1号に関しても自社で支援を行っている場合は費用がかかりません。
自社支援についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
⑥受入れできる分野
特定技能1号の受け入れ分野に関しては下記の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空、
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
※令和7年5月現在
2024年には新たに自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4つが追加されたため、多くの分野にて特定技能1号外国人が増加する見込みです。
特定技能2号の分野に関しては以下の11分野です。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※令和7年5月現在
このうち、造船・舶用工業分野は溶接区分以外の業務区分が対象となり、特定技能1号にあった介護は専門の在留資格「介護」があるため対象外とされています。
今後、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4つが追加されるかどうかについてはまだ未定となっています。将来的に追加される可能性もあるため、今のうちから特定技能1号の受け入れ態勢を整えておくことが必要でしょう。
また、特定技能1号に下記の分野が追加されるという最新情報も出ています。詳しくは下記の記事にてご確認ください。
⑦試験の難易度
試験の難易度に関しては、出入国在留管理庁が技能や経験、知識などを定めている通り、特定技能1号より特定技能2号の方がハードルが高くなります。
特定技能1号から特定技能2号へ移行したい場合は、余裕をもって試験を受け、早めに合格を目指すようにしましょう。特定技能2号の試験については下記の記事でまとめています。
⑧実務経験の有無
特定技能1号と2号についての大きな違いとして、実務経験の有無があります。
特定技能1号については特に実務経験は必要なく、試験に合格するか技能実習2号を良好に終了すれば申請ができますが、特定技能2号についてはそれぞれの分野での実務経験が必要です。
特定技能2号外国人は、基本的には管理や管理補助、監督などマネジメントができるレベル・ポジションである、もしくは高い技術があることが求められています。そのため、外国人の実務経験を記載する実務経験証明書の記入があります。
しかし、現時点で管理的な業務をしているにもかかわらず、明確に役職名がついていない場合も想定されます。その場合でも特定技能2号の移行は可能ですが、実務経験を証明する書類の提出を行い、それに基づいて判断がなされます。
特定技能1号と2号でかかる管理費はどのくらい違う?

特定技能1号と2号の違いとして気になるポイントとして、管理費があります。近年、自社支援に切り替える受け入れ企業が増加傾向にありますが、多くの受け入れ企業では特定技能1号の管理委託を管理団体に委託しているというケースがほとんどです。
特定技能1号と2号では、管理にかかるコストが大きく違ってきます。特定技能1号の支援を管理団体に委託した場合の平均コストは1名あたり2.8万円と言われており、例えば10名受け入れている場合については毎月28万がかかっているという計算になります。
しかし、特定技能2号についてはこの支援が義務とされていないため、管理団体に委託する必要がありません。そのため、実質支援委託にかかるコストは0ということになります。
特定技能1号と2号を比較すると管理コスト自体も大きな違いがあり、受け入れ企業としては特定技能2号が増加すればするほど負担は少なくなるという計算になります。
特定技能1号の受け入れが増加するにしたがって、膨らんだ管理費が経営や福利厚生の向上に支障があるという問題も発生しており、管理費を下げるために自社支援に切り替える受け入れ企業も少なくはありません。
特定技能1号と2号の採用にかかるコスト、人件費に違いはある?
特定技能1号と2号の採用にあたっては、初期コストや人件費に違いが出る場合があります。これらの違いを理解することで、企業はより適切な人材戦略を立てやすくなります。
採用コストの違い
| 特定技能1号 | 採用にかかる費用は、ビザ申請手続きや試験費用(個人負担と企業負担あり)、登録支援機関の管理委託費用などが中心です。 1号では、支援義務があるため、生活オリエンテーションや相談対応などの支援活動に伴うコストも発生します。これらは外部委託するケースが多く、年間数十万円~数百万程度の費用がかかることもあります。 |
| 特定技能2号 | 支援義務がなく、登録支援機関の利用も必須ではありません。また、日本国内からの採用が一般的になるため、採用コストと支援関連の費用は抑えられる傾向にあります。ただし、2号に移行するためには一定の技能水準を満たす必要があるため、試験に合格するための教育コストがかかる場合もあります。また、スキル的に転職しやすい人材のため受け入れ企業は待遇の向上が求められます。 |
人件費の違い
| 特定技能1号 | 比較的入国後間もない段階や、留学生等からの採用が多く、習熟度に応じて給与を段階的に引き上げるケースが多いです。教育やフォローアップに時間がかかりますが、初期の人件費は抑えられる傾向にあります。 |
| 特定技能2号 | より高度な技能と経験を持つことが多いため、給与水準が1号より高く設定されることが一般的です。2号を採用する場合、即戦力としての期待が大きいため、その分報酬も上がる傾向があります。日本人の管理職レベルの給与が必要になります。 |
採用コストや人件費は、特定技能1号・2号で異なる特徴があります。1号は支援体制にかかる費用がかかる一方、2号は高い技能を持つため人件費が高めになる傾向があります。企業のニーズや資金計画に応じて、どちらの在留資格を選ぶかを検討することが重要です。
1号と2号、どちらを雇用?企業の状況別おすすめパターンを紹介

特定技能1号と2号のどちらを受け入れるべきかは、企業の規模や事業内容、採用戦略によって異なります。以下に、企業の代表的な状況別におすすめの在留資格タイプを整理しました。
パターン①:初めて外国人材を受け入れる中小企業
- おすすめ:特定技能1号
- 理由:受け入れ手続きが比較的シンプルで、対象職種も多いため。特定技能外国人の人数が少ないうちは登録支援機関の活用で運用負担も軽減可能。
- 注意点:支援義務(生活ガイダンス、相談対応など)があるため、登録支援機関の選定が重要。また、受け入れ人数が多くなった場合や、長期化する場合は費用負担の点から自社での管理も検討する必要がある。
パターン②:長期的に外国人材を戦力化したい企業(大手企業、大量雇用を予定)
- おすすめ:特定技能1号→2号への移行を見据えた採用
- 理由:1号で育成し、2号への移行によって長期雇用が可能。家族帯同も視野に入るため、定着率が高まりやすい。また、大企業であれば自社での支援も人員的に可能となるため、計画的な雇用も可能。
- 注意点:特定技能外国人の数が増加するにつれ、登録支援機関への委託管理費も増大するため早めの自社管理への切り替えがポイント。
パターン③:すでに技能実習生を雇用している企業
- おすすめ:特定技能1号に移行して継続雇用
- 理由:技能実習2号修了者は条件さえ満たせば無試験で1号に移行可能。既存人材の経験・スキルを活かせる。また、既に雇用しているためミスマッチが起きずらい。
- 注意点:技能実習から特定技能への円滑な移行支援が必要。
特定技能の選び方には、以下のポイントがあります。
- 受け入れる予定の外国人は、現在どの技能水準にあるのか。
- 雇用する外国人に将来どのようになってほしいのか。
- 外国人本人はどのような働き方を望んでいるのか。
たとえば、受入れる外国人に特定技能外国人として長く働いてほしいのであれば、在留期間の上限のない特定技能2号を選ぶと良いでしょう。特定技能2号は、1号に比べて高度な業務もこなすことができます。また、支援の対象外であるため、1号よりも業務上・コスト上の受け入れに関する負担は減るでしょう。
ただし、受け入れたい外国人の技能水準が2号の条件を満たしていなければ、まずは特定技能1号として受け入れ、経験を積んだのちに2号へステップアップしていく流れとなります。そう考えると、まずは条件をクリアしやすい特定技能1号の方が受け入れやすいといえます。
将来的に特定技能2号の受入れを考える場合は、1号のうちから高い技術に達するようにサポートしていきましょう。特定技能1号のうちから、受け入れ企業が自社支援を行いサポートすることをおすすめします。
特定技能の1号と2号の申請方法の違いは?
特定技能の在留資格を取得するには、1号・2号それぞれで申請の流れや必要書類、手続き方法が異なります。ここでは、それぞれの申請方法について具体的に解説します。
特定技能1号の申請方法
特定技能1号は、外国人が日本で一定の専門的技能を活かして働くための資格です。申請手続きは以下のような流れで行います。
- 技能試験と日本語試験の合格(特定技能1号評価試験)
対象となる職種に応じて、指定された技能評価試験および日本語能力試験に合格する必要があります。試験の種類や受験方法は職種ごとに異なります。 - 就労先企業の決定
日本国内の受け入れ企業と雇用契約を結びます。 - 在留資格認定(もしくは変更)の申請
外国人もしくは受け入れ企業は、日本の出入国在留管理庁に「在留資格認定(変更)証明書交付申請」を行います。必要書類には、雇用契約書、技能試験合格証明、日本語試験合格証明などが含まれます。 - 在留資格の取得
審査が通り、在留資格を得たら受け入れ企業で働くことができます。外国人が海外にいる場合については、受け入れ企業のサポートの下で日本への入国が必要となります。
特定技能2号の申請方法
特定技能2号は、より高度な専門技能を持ち、長期的に日本での就労を希望する外国人向けの資格です。申請方法の流れは以下の通りです。
- 特定技能2号評価試験の合格
2号では、より高度な技能が求められるため、1号より難易度の高い試験に合格しなければなりません。試験内容は職種により異なります。 - 在留資格認定証明書の申請
1号と同様に、認定証明書の申請を行いますが、必要書類に加えて、より高度な技能を証明する書類や実務経験の証明が求められる場合があります。(※実務経験の証明書は、基本的に試験を受験する際に提出が求められる傾向にあります) - 在留資格の取得
審査を経て特定技能2号の在留資格が発行され、就労することができます。2号は家族の帯同が認められるため、長期的に日本での生活が可能となります。
以上が特定技能1号および2号の申請方法の概要です。どちらも多くの書類提出が必要なため、申請前に最新のガイドラインを必ず確認しましょう。また、書類作成については特定技能の書類が自動で作成できるツールの活用もおすすめです。
特定技能1号・2号に関する今後の動向は?

特定技能制度は、ここ数年で多くの変更や改善が進められています。特定技能を採用を検討する企業にとって、最新の動向を把握しておくことが非常に重要です。
① 特定技能2号の対象職種の拡大
- 2023年の閣議決定を受けて、介護・外食業・農業などの職種でも特定技能2号への移行が可能になりました。
- これにより、多くの分野にて外国人の長期雇用がしやすくなり、外国人材の生活基盤の安定化が進むと期待されています。
②技能実習制度の廃止・統合(新制度の創設)
- 2025年度以降、技能実習制度を廃止し、特定技能と統合した新制度(育成就労制度)が導入予定。
- 移行措置や経過措置が想定されており、今後の採用戦略に大きく影響します。
③出入国在留管理庁によるオンライン申請の推進
近年、出入国在留管理庁は手続きの効率化と利便性の向上を目的に、在留資格に関する申請のオンライン化を強力に推進しています。
これにより、特定技能1号・2号の申請手続きにおいても、従来の紙媒体による煩雑な申請に比べ、オンラインでのスムーズな対応が可能となっています。また、オンライン申請に対応する受け入れ企業に関しては手続きの簡素化を認めるなど、オンライン推進の動きは今後も続いていく見込みです。
④特定技能の支援については、2025年以降はより実態に即した内容へ
出入国在留管理庁や関係省庁は、2025年の4月に、制度変更について発表を行いました。オンライン定期面談の解禁や、定期届出、随時届出等が支援の実態に即した内容に変更されています。今後は、より現場の実態や業種特性に即した支援内容へのアップデートが進むと見られます。
特定技能1号と2号の条件を確認して受け入れましょう
以上、特定技能1号と2号の違いを解説しました。
技能水準が高く、長く在留できる特定技能2号は、受入れ企業と外国人のどちらにもメリットがあるのではないでしょうか。しかし、特定技能2号の条件を満たす外国人はまだ少数です。
今後も増えていくことが予想される人材ですので、受入れ企業は1号と2号の違いを理解し、企業にとってスムーズに受け入れができるように体制を整えておきましょう。
特定技能2号に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!
【詳細&お申込みはこちらから】
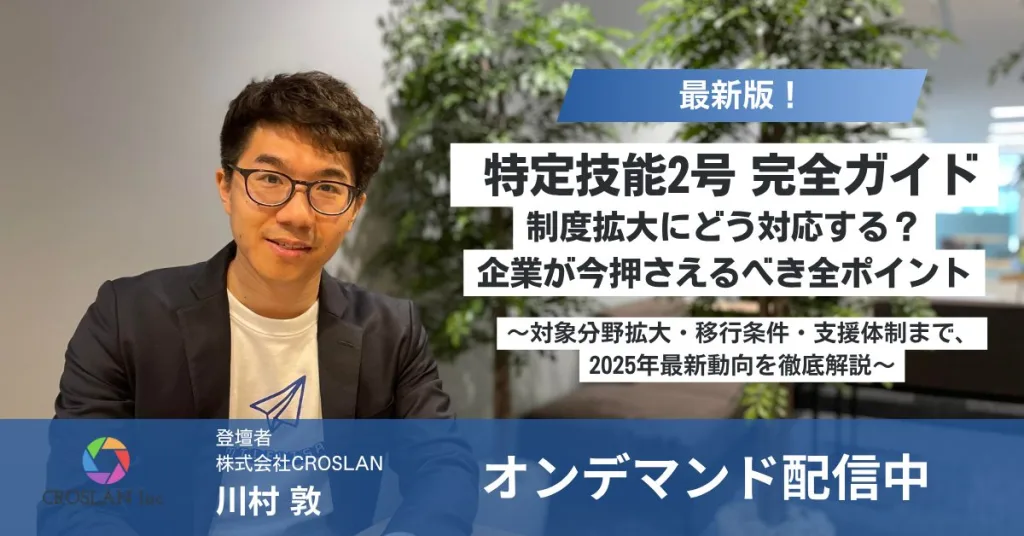
※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。
また、以下の記事でも特定技能2号について解説されておりますので、併せてご覧ください。
▶︎特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!|Jinzai Plus
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
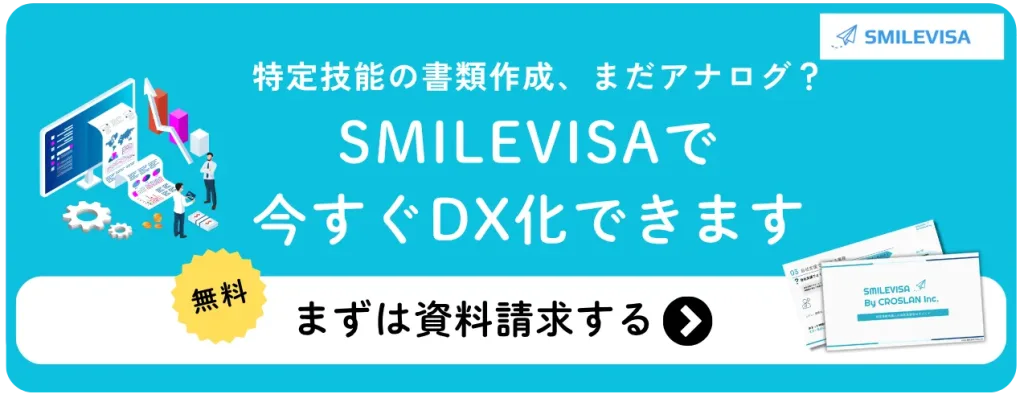
※本記事は現時点(2025年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。