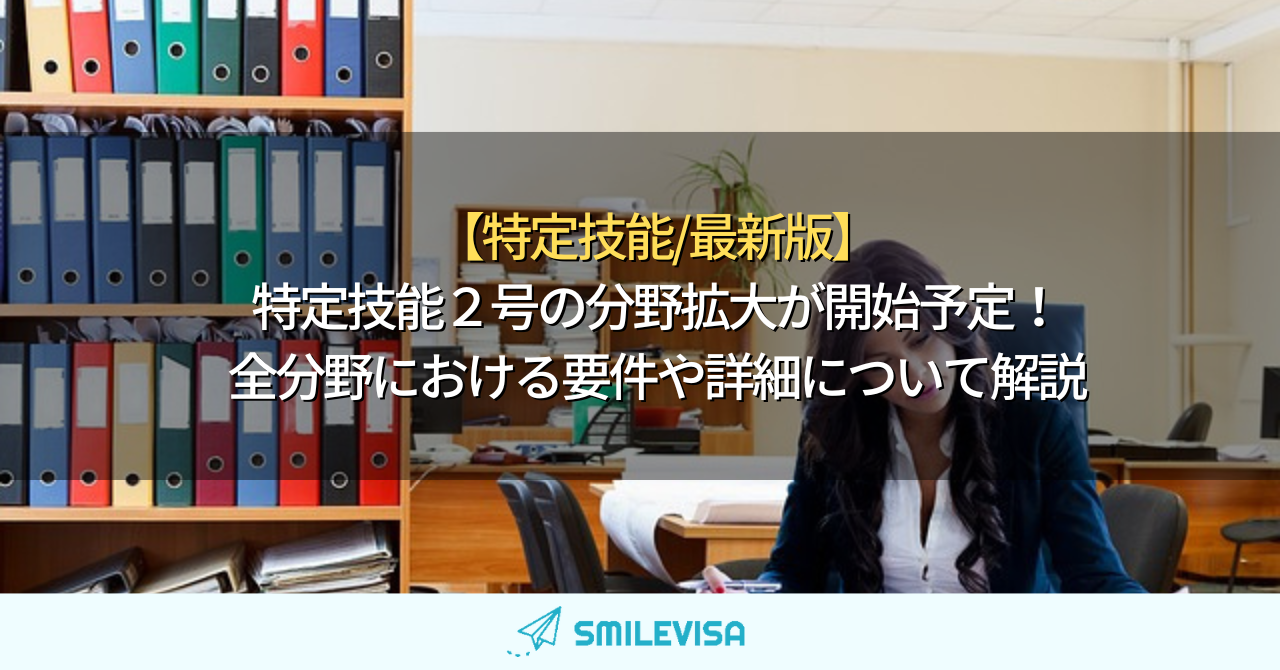目次
みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
詳しくはこちらの記事で紹介しています
→【速報】特定技能2号拡大の可能性が高まる!開始時期はいつから?対象の職種についてまとめ
2024年の時点では、特定技能1号の12分野のうち「建設分野」と「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみが特定技能2号の対象となっていましたが、新しい方針では「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に加えて、秋以降(もしくは来年以降)に下記の業務区分すべてが特定技能2号の対象に加わります。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
※介護分野は専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象にはなっていません。→介護の資格についてはこちら(【外国人の介護就労資格】技能実習・特定技能・介護・EPAの違いとは?わかりやすく解説)で詳しく解説しています
分野ごとの要件については、6月9日に改正された運用要領ですでに公表されており、2023年8月31日に運用要領としてさらに詳細が追加され、施行されています。詳しくはこちらのページにて確認ができます。
受入れ企業にとって特定技能2号の拡大は、今後の特定技能外国人の支援体制に大きく関係してくるのではないでしょうか。
特定技能2号になるための、それぞれの分野での移行要件を確認していきましょう。
→最新情報のアップデートについてはメルマガでも随時お知らせしています。この機会に是非ご登録ください。
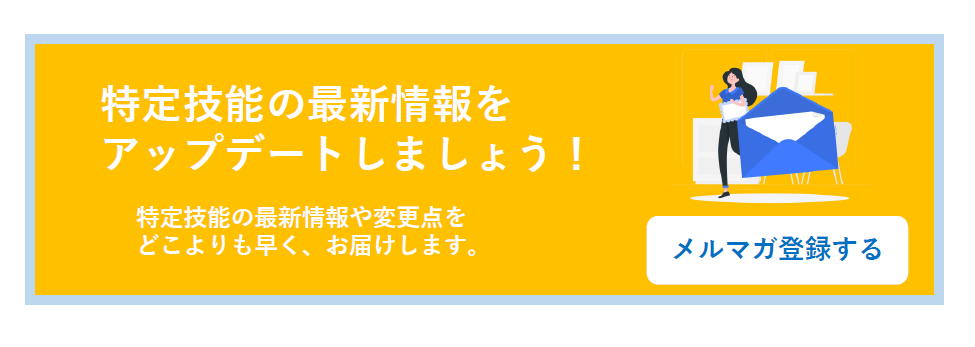
ビルクリーニングの特定技能2号への移行要件
ビルクリーニング分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の特定技能2号への移行要件
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
建設の特定技能2号への移行要件
建設分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
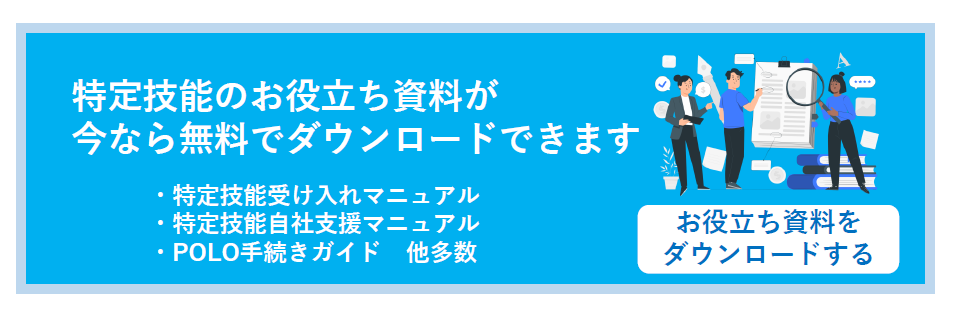
造船・船用工業の特定技能2号への移行要件
造船・船用工業分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
自動車整備の特定技能2号への移行要件
自動車整備分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
航空の特定技能2号への移行要件
航空分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
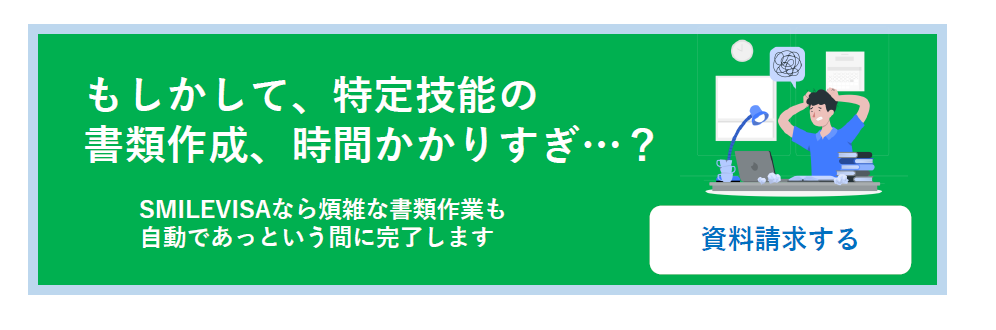
宿泊の特定技能2号への移行要件
宿泊分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
農業の特定技能2号への移行要件
宿泊分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
漁業の特定技能2号への移行要件
漁業分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
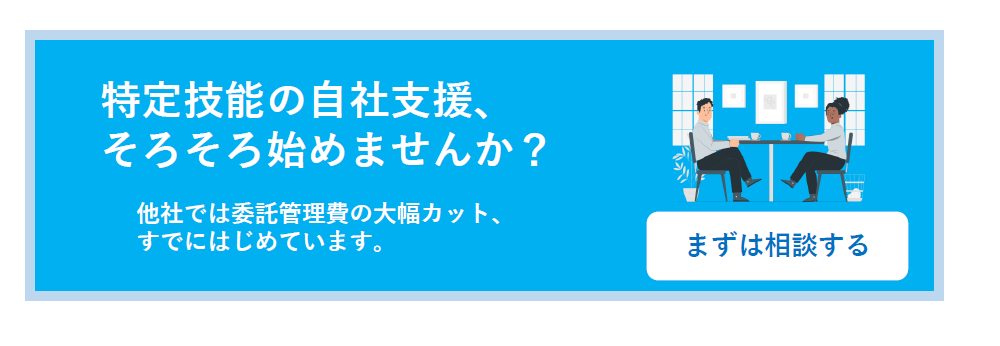
飲食料品製造業の特定技能2号への移行要件
飲食料品製造業の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
外食業の特定技能2号への移行要件
外食分野の特定技能2号への移行についてはこちらの記事にてまとめています。
改正される制度に向けて今から準備をしていきましょう!
以上、特定技能2号の分野拡大について、それぞれの分野で特定技能2号に移行するための詳細をお伝えしました。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
また、特定技能2号に関するセミナーも開催しています。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!
【詳細&お申込みはこちらから】
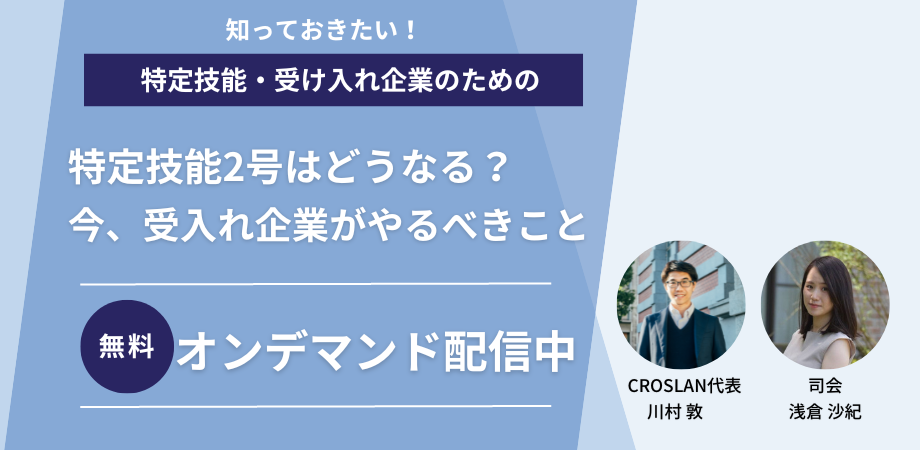
※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
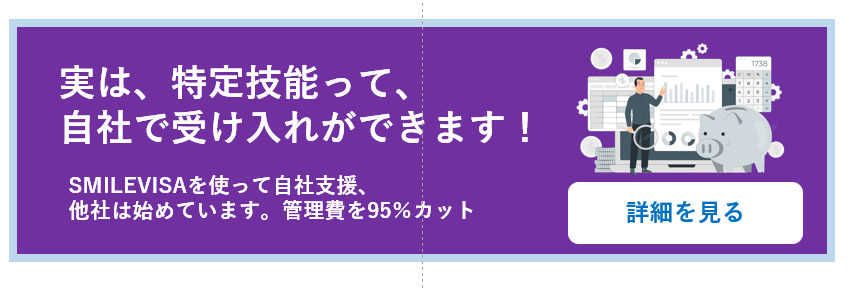
※本記事は現時点(2024年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。